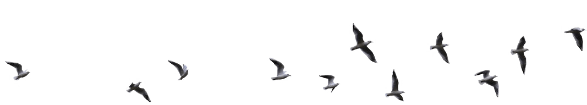2025.07.05
AI時代に、なぜWebサイトがますます重要なのか?〜AIに選ばれるための考え方(LLMO)〜

近年、ChatGPTをはじめとする生成AIの普及により、情報の調べ方が大きく変わりつつあります。これまでのようにキーワードを検索エンジンに入力して調べるだけではなく、「おすすめの会社を教えて」とAIに直接質問するユーザーが急増しています。こうした対話型AIに企業が“選ばれる”には、Webサイトに掲載する情報の質や信頼性が極めて重要です。
この記事では、AIに紹介される企業になるための考え方「LLMO(Large Language Model Optimization)」を軸に、Webサイトの整備で押さえるべきポイントなどをご紹介します。
「検索」から「会話」へ。変わりゆく情報収集のかたち
これまで、ユーザーが企業やサービスを比較・検討する際には、Googleなどの検索エンジンで例えば「タイ 会計事務所 比較」「バンコク 物流会社 おすすめ」といったキーワードを入力し、検索結果をもとに判断するのが一般的でした。
しかし最近では、ChatGPTのような生成AIに例えば「タイで信頼できる日系会計事務所を教えて」といった自然な言葉で“尋ねる”人が増えています。検索から対話へ──自社が選ばれるまでのプロセスが、大きく変わり始めているのです。
では、AIはどこからその情報を得ているのでしょうか?
ChatGPTなどの生成AIは、インターネット上にある大量のテキストデータ(企業のWebサイト、ニュース記事、口コミサイト、業界ポータルなど)を学習しています。つまり、オンライン上に十分な情報が存在しなければ、AIはその企業を“存在していない”ものとして扱ってしまうのです。
これは、検索エンジン対策(SEO)以上に本質的な課題です。AIが“何を、どのように見て、どう紹介するか”という視点から、自社の情報発信を見直す必要が出てきていると言えます。
AIに“紹介される”ために必要な新しい視点「LLMO」とは?
こうした背景から、近年注目されているのが「LLMO(Large Language Model Optimization:大規模言語モデル最適化)」という考え方です。
これは、ChatGPTのような生成AIに自社の存在やサービス内容を正しく認識してもらい、「おすすめの会社は?」「信頼できるパートナーは?」といった質問に対する回答の中で、自社が紹介される状態を目指す情報発信の最適化手法です。
例えば、ユーザーがChatGPTに「タイで実績のある通訳サービスを教えて」と聞いたとき、AIが自社を候補として挙げてくれるには、その企業に関する十分な情報がインターネット上に存在し、かつ信頼性のある形で整理されていることが前提になります。
つまり、Webサイトがあっても内容が薄かったり、具体的な活動情報やサービスの説明がなかったりすると、AIはその企業を“認識できない”か、“回答の対象として適切ではない”と判断してしまうのです。
従来のSEO(検索エンジン最適化)は、Googleで検索したときに自社のページが上位に表示されることを目的としていました。
一方、LLMOは、「AIが質問に対して回答を生成する際に、自社の情報を元にした言及をしてくれるかどうか」がポイントになります。つまり、“見つけてもらう”のではなく、“選ばれて紹介される”ことを重視するという違いがあります。
これは、例えるなら「検索結果の一覧に並ぶかどうか」ではなく、「AIが答える数行の中に入れるかどうか」の勝負とも言えます。しかも、生成AIは一度に紹介できる企業数を絞り込むため、“選ばれる・選ばれない”の差が従来以上に大きくなる傾向があります。
LLMOはまだ比較的新しい概念ですが、生成AIの利用が広がるにつれて、企業のオンライン上での“見つけられ方”や“信頼の築き方”にも大きな影響を与えるようになっています。
企業の広報やマーケティング担当者にとっては、従来のSEOや広告に加え、「AIがどのように情報を理解し、回答を組み立てるか?」という視点でWebサイトを見直すことが、これからますます重要になっていくでしょう。
「LLMO」と「SEO / AI SEO」の違いとは?
「LLMO」とよく比較される概念に、「AI SEO(生成AI時代のSEO)」があります。どちらもAIに“見つけてもらう”ための情報発信という点では共通していますが、対象とするAIのタイプと、情報の扱われ方に大きな違いがあります。
従来のSEO、そして近年注目されているAI SEOは、GoogleやBingなどの検索型AIに対応するための施策です。これらは、ユーザーが検索エンジンにキーワードや質問文を入力した際に、自社のWebページが検索結果の上位に表示されることを目的としています。
2024年頃からは、Google検索において「AI Overview(SGE)」と呼ばれる機能が導入され、従来の検索型体験と生成AIによる要約が組み合わされた、検索と対話のハイブリッドのような形式が広がりつつあります。
とはいえ、その基本的な構造はあくまで「検索結果の中からユーザーに選んでもらう」ことを前提としており、情報の出し方も依然として“見つけてもらう”ことに軸を置いたアプローチである点は変わりません。
つまり、「検索結果の一覧の中で、いかに目立つか」「クリックしてもらえるか」が成果の指標となる、検索型AI時代における情報最適化といえます。
一方で、LLMOが対象とするのは、ChatGPTのような対話型AI(大規模言語モデル)です。ここではユーザーが「〇〇に強い会社を教えて」と自然な言葉で質問を投げかけたとき、AIが回答として数社だけを“推薦する”形式になります。つまり、“紹介されるかどうか”がすべてで、順位やクリック率ではなく、「その企業が答えの中に含まれるかどうか」が問われるのです。
この違いを一言でまとめるなら、
・AI SEOは“検索に強くなる”ための施策
・LLMOは“AIの回答に含まれる”ための施策
といえるでしょう。
どちらか一方だけが重要というわけではなく、検索にも対話にも対応する“二層構え”の情報発信が、これからの企業広報に求められています。
自社のWebサイトがAIに「認識」されるためには?
ただWebサイトがあるだけでは、AIに企業の存在や活動を正しく認識してもらえるとは限りません。AIはインターネット上の膨大なテキスト情報をもとに学習しており、サイトの構造や書かれている内容によって「どんな会社か」「何をしているのか」を判断しています。
しかし、情報が整理されていなかったり、発信内容が不十分だったりすると、AIがその企業を適切に認識できず、紹介対象として扱われにくくなってしまいます。
AIに「実在する企業」としてきちんと認識されやすくするために、Webサイトで意識すべきポイントをご紹介します。
①網羅性:必要な情報がきちんと揃っているか
AIは断片的な情報だけでは企業の実態を理解できません。会社概要、サービス内容、対応エリア、実績、連絡先、導入事例など、基本的な情報を過不足なく掲載しておくことが大前提です。
例えば以下のような情報は、特に明記しておくことが重要です。
・どんなサービスを提供しているのか(業種・内容)
・どの地域を対象としているのか(例:タイ全土、バンコク、日系企業向けなど)
・実績や事例(業界、規模、成果など)
・お客様の声、スタッフ紹介、会社の雰囲気が伝わる情報
② 自然な文章:人が読んでわかりやすい言葉で
AIは自然言語処理に優れていますが、読みづらい文章や不自然なキーワードの詰め込みには弱くなります。人間が読んで理解しやすい自然な文章で、誰に向けて何をしている会社なのかが伝わるようにしましょう。
・単語を並べただけの見出しや、SEO目的だけの羅列は避ける
・「〜についてご紹介します」といった文脈を意識して説明する
また、AIは「信頼性のある情報源」かどうかを重視します。公式サイトらしいトーンや文体、整ったデザイン、正確な会社情報(住所、連絡先、代表者名など)の記載が、AIにとっても「信頼できる企業」と判断されやすい要素といえます。
③ 整理された情報構造:AIが情報を正しく把握しやすい構造に
AIは人間と同様、整理された情報構造を好みます。たとえば、ページ内の見出しがしっかり階層化されていたり、各情報が適切なまとまりごとに整理されていることで、「何が主で、何が補足か」を正確に理解しやすくなります。
これは単にHTMLのタグやコードの話ではなく、**Webページ全体の論理的な構造=入れ子構造(セクション構造)**が重要ということです。
たとえば:
・サイト全体の階層構造をわかりやすく整理
・h1(ページ全体のテーマ)→ h2(各サービス)→ h3(サービスごとの特徴)といったページ内の階層整理
・会社概要ページでは、所在地・代表者・設立年などをまとまりとして一覧表示
・長文のページでは、冒頭に要点を整理したまとめブロックを用意する
このように、「情報の整理のされ方」そのものが、AIにとっての“認識のしやすさ”に直結します。
参考記事:
WEBサイトの成否は初期設計で決まる!? WEBサイトにおける構造化の重要性 >>
④ Q&A構造:質問形式の見出しでAIにも伝わりやすく
AIは、人間の質問に答えるかたちで情報を生成します。そのため、Webサイト内のコンテンツも「質問形式の見出し」と「それに対する明確な回答」という構造になっていると、AIにとって非常に理解しやすくなります。
大きな構造設計やコンテンツの網羅には時間がかかりますが、見出しの書き方を少し工夫するだけでも、AIにとっての認識精度を高めることができます。
たとえば:
・「◯◯サービスとは何?」
・「この製品はどんな課題を解決しますか?」
・「導入までにどれくらいの期間がかかりますか?」
といった質問形式をコンテンツの見出しに据えるなどです。
これは、ChatGPTのような対話型AIが質問への回答をベースに情報を生成するという特性に合致した、“伝わる見出しの書き方”というテクニック的アプローチとして有効です。
FAQページやコラム記事に限らず、サービスページや会社案内などにも応用できるため、小さな工夫ながら効果的な改善ポイントといえるでしょう。
⑤ 一次情報:信頼できる発信元であることを示す
AIは信頼性を重視します。外部サイトからの転載ではなく、自社が直接発信している一次情報をベースにしたコンテンツは、AIにとっても価値が高いと判断されます。
・実際の事例、導入成果、社内ノウハウなどのオリジナルコンテンツを積極的に発信
・著者情報や運営者情報を明記する(企業名・責任者・プロフィールなど)
自社の言葉で発信された実体験に基づく情報は、AIにとって「その企業ならではの視点」「信頼できる根拠」として評価されやすくなります。特に、他社では入手できない独自の事例や、専門性の高い知見をコンテンツとして発信することで、AIがその企業を“専門的な知識を持つ存在”として認識する土台が築かれます。
AIが信頼性を判断する具体的なポイント
AIに「信頼性が高い情報」として扱われるかどうかには、いくつかの具体的な指標が影響しています。これはGoogleの「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)」に似ていますが、AIではさらに文脈的・構造的な要素も加わります。
1. 情報の出どころ(発信者の属性)
・誰がその情報を発信しているか?
・企業の公式サイトなのか、個人ブログなのか?
・専門家による執筆かどうか?
2. 著者情報・運営者情報が明示されているか
・記事に著者名が記載されている
・プロフィールページがある
・会社概要、責任者、連絡先が明示されている
匿名性の高いサイトや記事は、AIにとって信頼性が低いと判断されがちです。
3. 構造と文体が“オフィシャル”である
・正しい日本語/英語で丁寧に書かれている
・無理な誇張やスパム的表現がない
・段落構成や見出しが整理されている
AIは自然言語の構造を重視します。「専門的な情報が、読みやすく、整った形式で提供されている」ことでAIからの信頼を得やすくします。
4. 第三者による言及・リンク・掲載
・他のメディアや業界サイトで紹介されているか
・SNSや他ブログで引用されているか
・Wikipediaなど中立的・信頼性の高いソースに載っているか
これは人間にとっても納得感がある「裏付け情報」の役割を果たします。
5. 情報の一貫性と更新頻度
・会社や著者の他の記事・ページと整合性がある
・古い記事に更新が加えられている
・サイト全体として“動いている”印象がある
AIも「最近の情報かどうか」「放置されたサイトではないか」をチェックする傾向があります。
LLMOで大切なのは実績と信頼の「積み重ね」
LLMOにおいては、一度の発信で信頼を勝ち取るのは難しいという点をまず理解しておく必要があります。
AIは、ユーザーに代わって企業やサービスを紹介する“代弁者”のような存在です。つまり、AIにとって「この企業は紹介に値する」と判断するには、それ相応の信頼材料が求められるということです。
この構造は、人が友人に何かを紹介する場面にも似ています。誰かにおすすめを聞かれたとき、1回だけ見た広告や、情報が少ないサービスを紹介するのはためらわれるでしょう。繰り返し見聞きし、信頼できると感じたものだけを紹介したくなる──AIも同じように“積み重ね”を重視して判断しているのです。
たとえば、自社のWebサイトに掲載されている記事が、
・1本きりで更新が止まっている
・他のページとの関連性が薄く、情報が点在している
・出典や具体性に欠ける
といった状態だと、AIは「たまたま存在するだけの情報かもしれない」と判断し、紹介候補から外してしまうことがあります。
逆に、継続的に、信頼できる視点で情報を発信している企業であれば、それ自体が「実在性」「専門性」「誠実さ」の証明となり、AIからも高く評価されやすくなります。
・定期的な更新 → “今も活動している企業”としての存在証明
・専門的な視点からの発信 → その分野に詳しいという裏付け
・偏らない・正確な情報 → 誠実で信頼できる姿勢の表れ
このように、地道な情報発信の積み重ねが、その企業を「紹介に値する存在」としてAIが“認識”し、“選ぶ”根拠になります。
AI、検索エンジン、ユーザーのすべてに共通して重要なのは、「この企業が誰に、どれだけの実績をもって、何を伝えているのか」という継続的な情報の積層です。
単発のテクニックではなく、“信頼される存在としての厚み”を、時間をかけて築いていくこと。
それこそが、最終的にAIに「この企業は紹介にふさわしい」と判断される鍵なのです。
まとめ
AIに見つけてもらうためには、まず人間にも伝わりやすいWebサイトである必要があります。わかりやすく整理された内容、丁寧に書かれた紹介文、信頼感のあるデザインと情報。それはAIにとっても、「この会社は紹介に値する」と判断する材料となります。
SNSや口コミももちろん大切ですが、最終的にユーザーやAIがたどり着くのは「公式Webサイト」です。企業のアイデンティティを伝える最前線としての役割を、Webサイトはいま一度見直すべき時期に来ているといえるでしょう。
「自社のWebサイト、AIにちゃんと伝わる内容になっているだろうか?」
そんな視点から、サイトの見直しをしてみるのも一つの第一歩です。
関連記事
-

SEOライティングとコピーライティングの違いとは?役割と目的の徹底比較
SEOライティングとコピーライティングの違いをご紹介します。それぞれの特徴を理解し、目的に合わせて使い分けられるようになれば、Webコンテンツの成果も大きく変わってきます。
2025.07.12 #SEO / LLMO対策 -

更新頻度が検索順位に与える影響とは?定期的な更新がもたらすSEO効果を解説
Webサイトの検索順位を上げるには、コンテンツの質やキーワード設計、被リンクなどさまざまな要素が関わってきますが、「更新頻度」も見逃せないポイントのひとつです。コンテンツの更新頻度とSEOの関係について解説します。
2025.05.11 #SEO / LLMO対策 -

AIで書かれたSEOコンテンツは検索上位表示できない?
WEBサイトの文章をAIで書いた際、検索結果の表示に影響があるのかと考えたことはありませんか?この記事では、AI生成コンテンツとSEOの関係性を解き明かしながら、WEBサイトの運営にAIをどのように活用すべきかを考察します。
2024.11.24 #SEO / LLMO対策 -

WEBサイトの成否は初期設計で決まる!? WEBサイトにおける構造化の重要性
WEBサイトを作る際、デザインやコンテンツに注目しがちですが、成果につながるWEBサイトとするために重要な概念がWEBサイトの「構造化」です。 そのWEBサイトづくりの基本ともいえるWEBサイトの構造化について解説します。
2025.03.11 #WEBサイト制作