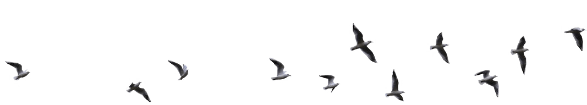タイで注目のBtoBオウンドメディア活用術|日系企業がタイ市場で成果を上げるための基本と戦略

タイに進出している日系企業の間でも、従来のコーポレートサイトに加えて、情報発信型のオウンドメディアを活用する動きが広がっています。一方で「コーポレートサイトと何が違うのか?」「うちのサイトでもオウンドメディア的な発信をしているけど、それで合っているのか?」と感じている広報・マーケティングご担当者の方も多いのではないでしょうか。
この記事では、オウンドメディアと企業のホームページの違いを整理しながら、タイ市場で日系企業がオウンドメディアを使った情報発信を成功させるためのヒントをお伝えします。
オウンドメディアとは?トリプルメディアの中核を担う情報発信手段
「オウンドメディア」という言葉を耳にしたことはあるけれど、実際に何を指すのかはよくわからない――そんな方も多いかもしれません。
企業の情報発信においては、「トリプルメディア」と呼ばれる3つのメディアの使い分けが重要とされています。
1. オウンドメディア(Owned Media)とは
オウンドメディアとは、自社が保有し、自由に情報を発信・運用できるメディアのことです。ブログや特集ページ、事例紹介、FAQサイトなど、自社の視点で企画・制作されたコンテンツを通じて、ブランドの世界観や価値を中長期的に伝える「資産」として活用できます。
たとえば、以下のようなものが該当します。
・製品紹介や使い方を紹介する企業ブログ
・業界トレンドやノウハウを伝えるコラム
・導入事例をまとめた特集コンテンツ
・よくある質問や学習資料を掲載するFAQサイト
これらはすべて、広告のように一時的な効果に頼らず、自社の強みや思想を継続的に発信することで、信頼構築やファン化を促す重要なマーケティング基盤となります。
2. ペイドメディア(Paid Media)とは
ペイドメディアは、広告費を支払うことで露出を得るメディアのことです。
例:Google広告、SNS広告、テレビCM、バナー広告など。
即効性が高く、新規顧客へのリーチに有効ですが、発信内容の自由度や継続性には限界があります。
3. アーンドメディア(Earned Media)とは
アーンドメディアは、ユーザーや第三者からの評価や共感によって得られる自然発生的なメディア露出のことを指します。
例:SNSでの口コミ・シェア、レビュー、ニュース記事での紹介など。
信頼性が高く拡散力もありますが、自社でコントロールしにくい点が特徴です。
各メディアのメリット・デメリット比較
| 種類 | 保有者 | 主な例 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|---|
| オウンドメディア(Owned Media) | 自社 | ウェブサイト、ブログ、パンフレット | 中長期的な信頼構築、発信自由度が高い | 立ち上げ・運用に手間がかかる |
| ペイドメディア(Paid Media) | 他社 | 広告(Web、TV、新聞など) | 即効性がある | 広告費がかかり続ける |
| アーンドメディア(Earned Media) | 第三者 | SNS投稿、口コミ、レビュー | 信頼性・拡散力が高い | 意図的に発生させにくい |
なぜ今、オウンドメディアが重視されているのか?
オウンドメディアは“すぐに成果が出る施策ではなく”、継続的な運用や一定のリソース・スキルが求められるという課題があります。それでも多くの企業がオウンドメディアを重視するのには、以下のような長期的視点に立った合理的な理由があるからです。
1. 広告依存からの脱却=持続可能な集客チャネルを確保できる
広告は出稿を止めれば即座に集客が止まる「瞬発型」の施策ですが、オウンドメディアはコンテンツを積み重ねることで効果が蓄積していく「持続型」のチャネルです。記事やコラムは一度公開すれば、検索結果に長期間表示され続ける可能性があり、時間とともに自然流入を生み出す“資産”となります。
もちろん、立ち上げ期だけでなく、継続的なコンテンツの企画・制作には一定の労力とコストがかかります。また、内容の質を担保しつつ更新を続けるには、内製する場合でも体制構築やスキル育成が欠かせず、属人的な運用にしないための仕組みづくりも必要です。
それでも、広告にはないメリットがあります。ユーザーの疑問に寄り添う記事や、自社の思想や実績を伝えるストーリーは、単なるクリックでは得られない“信頼”や“共感”を生み出します。こうした中長期的な価値が、オウンドメディアの大きな強みです。広告費を抑えながら、ブランド価値を高めつつ継続的な集客を実現する。そんな“持続可能な集客基盤”として、オウンドメディアは今あらためて注目されています。
2. 顧客に“選ばれる理由”をきちんと伝える場として機能する
比較検討の段階にある顧客は「この会社は信頼できるか」「他社との違いは?」を知りたがっています。
広告では語りきれない価値観・ノウハウ・実績を丁寧に伝えられるメディアとして、オウンドメディアが活躍します。
3. ノウハウや事例の“社内共有・営業支援ツール”にもなる
対外的な発信だけでなく、営業現場で使える資料やFAQの集積所としての役割も果たします。
特にBtoB領域では、営業と連動したオウンドメディア活用で効率的な受注活動が可能になります。
4. 時間はかかるが“広告よりも高い費用対効果”を実現できる
SEO施策は結果が出るまでに一定の時間を要しますが、いったん検索上位に表示されるようになると、広告費をかけなくても継続的にアクセスを集められるのが大きな特長です。たとえば、記事コンテンツを継続的に作成・運用した場合、半年〜1年後には検索結果の上位に表示され、その後も自然検索からの流入が安定して続くことがあります。広告のようにクリックのたびに費用が発生することもなく、コンテンツが資産となって長期的に効果を発揮するため、結果として広告以上の費用対効果が期待できます。中長期的な視点で見ると、SEOは広告に比べて非常に効率の良いマーケティング手法といえます。
5. 顧客との関係性が“浅い接点”から“深い信頼”に変化する
オウンドメディアは、SNSや検索から訪れたユーザーに対して、自社の考え方や取り組み、実績などをじっくりと伝えられる場です。単なる商品紹介やセールスではなく、継続的に価値ある情報を提供することで、ユーザーは「この会社は信頼できそう」「ここに相談してみたい」と感じるようになります。こうした“共感”や“納得”を積み重ねることで、最初は偶然の接点だったユーザーが、自社に関心をもち、やがてファンや顧客となっていくのです。これは短期的な広告や販促では得られにくい、オウンドメディアならではの強みであり、ブランド価値を着実に高めていくための本質的なアプローチといえます。
オウンドメディアとコーポレートサイトとの違いを理解しよう
広い意味では、企業が自ら所有・運営するウェブサイト全般を「オウンドメディア」と呼び、コーポレートサイトもその一つに含まれます。しかし、実際の運用目的やコンテンツの性質には明確な違いがあります。
コーポレートサイトは、会社概要、事業内容、採用情報、IR情報など、企業としての公式情報を発信する場として機能します。主な目的は、企業としての信頼性を担保し、取引先や求職者、ステークホルダーに対して基本情報を提供することにあります。
一方、オウンドメディア(狭義)は、コンテンツマーケティングの文脈で使われることが多く、ユーザーの関心を引く情報発信を通じて、新たな接点の創出や関係性の構築、ファン化、最終的な購買・問い合わせにつなげることを目的としています。たとえば、業界トレンド、課題解決のヒント、事例紹介など、読み物として価値のある記事を通じて、潜在層のニーズにアプローチします。
つまり、コーポレートサイトが「企業を知ってもらうための場所」だとすれば、オウンドメディアは「ユーザーとの関係を深めるための場」といえるでしょう。それぞれの役割を明確に理解し、目的に応じて使い分けることが、効果的なWEB戦略には欠かせません。
| 比較項目 | コーポレートサイト | オウンドメディア |
|---|---|---|
| 目的 | 信頼性のある会社情報の掲載(企業概要・採用・IRなど) | 潜在顧客との接点づくり・集客・ファン化 |
| ターゲット | 取引先・求職者・投資家など | 検索ユーザー・SNS閲覧者・潜在顧客など |
| 更新頻度 | 低い(必要時のみ) | 高め(定期的な更新が前提) |
タイ市場でオウンドメディアを導入する際に考えるべきポイント
タイでオウンドメディアを立ち上げる際は、日本と同じ感覚で進めるのではなく、現地の文化や言語、ユーザー行動に配慮した設計が不可欠です。成功させるためには、ターゲット、導線、運用の3つの視点から戦略的に取り組む必要があります。
1. 発信するターゲットを明確にする
最初に重要なのは、「誰に向けて情報を発信するのか」を明確にすることです。たとえば、タイ人消費者を対象にするのか、日本人駐在員や現地日系企業の担当者を対象にするのかによって、使う言語(タイ語・英語・日本語)、コンテンツのトーン、情報の深さが大きく変わってきます。
また、BtoC向けかBtoB向けかによってもアプローチは異なります。ターゲットを絞ることで、情報が刺さる精度が高まり、結果として検索順位や問い合わせ率の向上にもつながります。
2. 導線設計とコンテンツ戦略を考える
タイ市場に合ったテーマ設定とコンテンツ導線の設計も欠かせません。製品紹介や導入事例に加え、業界の動向、ノウハウ系の記事など、検索ニーズやSNSで拡散されやすい切り口を検討しましょう。
タイではFacebookやLINEの利用率が非常に高いため、検索からだけでなくSNS経由での流入を前提にした導線設計が有効です。記事を読んだあとのアクション(問い合わせ、資料請求、関連ページへの遷移など)まで設計できているかを意識することが重要です。また、単なる翻訳ではなく「ローカライズ」によって、自然で現地ユーザーに刺さる表現にすることも忘れてはなりません。
3. 継続的に運用できる体制と改善サイクルをつくる
オウンドメディアは作って終わりではなく、公開後からがスタートです。月1〜2本の更新からでもよいので、継続的に情報発信し、タイミングや反応を見ながら改善を重ねていく姿勢が求められます。
運用には、現地語での執筆・翻訳体制、SNSへの連携、記事のスケジューリングなどが関わるため、社内の担当者だけで抱え込まず、外部のパートナーと連携して進めるのが現実的です。さらに、Google AnalyticsやSearch Consoleを活用して、どのコンテンツが成果を上げているかを定期的に可視化し、次の施策に反映していくPDCAサイクルの確立が成功のカギになります。
コーポレートサイト×オウンドメディアの相乗効果を狙おう
コーポレートサイトとオウンドメディアは、単体でもそれぞれの役割を果たしますが、連携させることでより高い成果を生み出すことができます。コーポレートサイトが企業の信頼性や基本情報を伝える「名刺代わり」の役割を担う一方で、オウンドメディアはユーザーとの接点を広げ、関係を深める「会話のきっかけ」となる存在です。
たとえば、オウンドメディアで製品の導入事例や業界の課題を掘り下げた記事を公開し、そこから詳細情報を掲載するコーポレートサイトのサービスページへ自然に導線をつなぐことで、ユーザーはより深く企業理解を進められます。逆に、コーポレートサイト上でも、関連する読み物としてオウンドメディアの記事を紹介することで、ページの滞在時間や回遊率の向上にもつながります。
さらにSEOの観点から見ても、両サイトの内部リンクを適切に設計することで、検索エンジンからの評価を高める効果も期待できます。情報発信と信頼獲得、集客とコンバージョン。それぞれの強みを活かしながら連携させることで、デジタルマーケティング全体のパフォーマンスを大きく底上げできるのです。
例:
・製品紹介ページに、使用事例や関連コラムへの導線を追加
・採用ページに、社員インタビュー記事を掲載して共感を得る
・SNS広告から、オウンドメディア記事に誘導して顧客育成を行う ・・・etc
まとめ:タイ市場でオウンドメディアを活かすために
オウンドメディアは、単なる情報発信の場ではなく、ターゲットとの関係を築き、信頼を獲得し、最終的なアクションにつなげるための重要なマーケティング資産です。特にタイ市場では、検索やSNSの利用傾向、言語や文化の違いを理解したうえで、戦略的に設計・運用することが成果につながります。
また、コーポレートサイトとの連携により、情報の「深さ」と「広がり」を両立させることで、ユーザー体験を高め、企業の信頼性や魅力を効果的に伝えることができます。
短期的な成果を求めがちな時代だからこそ、オウンドメディアという「長期的に効く資産」をしっかり育てていくことが、他社との差別化や競争優位の確立に直結します。タイ市場でのブランド価値を高めたい企業にとって、今こそオウンドメディアの本格的な活用が求められています。
関連記事
-

タイBtoB市場におけるデマンドジェネレーションの活用とその有効性
タイでBtoB企業の市場拡大、拡販をしたいとお考えのマーケティング担当者の方の中にデマンドジェネレーションを活用したいという方が増えています。 ここでは、デマンドジェネレーションの基本的な考え方をはじめ、タイ市場においてデマンドジェネレーションを活用する際の留意点などをご紹介したいと思います。
2024.02.17 #デジタルマーケティング -

BtoBのWEBサイト制作に求められるデザイン性とは?
BtoBのWEBサイトは、単なる情報提供の場ではなく、ビジネスパートナーシップを築くための重要なコミュニケーションツールと言えます。これらのWEBサイトにおいてデザイン性は、単なる視覚的な魅力だけでなく、企業の信頼性や使いやすさにも直結しています 今回は、BtoBのWEBサイトに求められるデザイン性について考察してみます。
2024.06.01 #BtoBマーケティング#WEBサイト制作 -
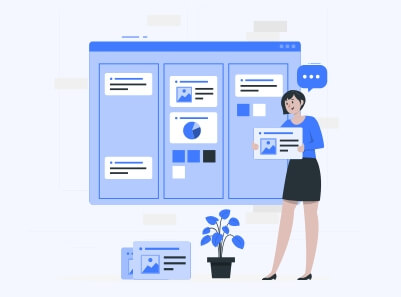
BtoBマーケティングを加速する!ホワイトペーパーの作り方と活用術
ホワイトペーパーとは何か、なぜ今注目されているのか、そして実際にどのように作成・活用すれば効果的なのかを、タイで事業を展開する広報・マーケティング初心者の方にもわかりやすくご紹介していきます。
2025.06.23 #BtoBマーケティング#デジタルマーケティング