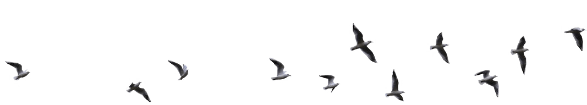生成AIで作る画像・動画を商用利用するときに、WEB担当者が押さえておきたいポイント

生成AIを使って広告バナーの背景やLP用のイメージ、さらにはSNS向けの短尺動画まで作れるようになり、制作現場ではAI活用が「日常の選択肢」になってきました。一方で、クライアントや企業側では、「本当に使って大丈夫なのか?」「どこまで商用でOKなのか?」といった不安や抵抗が根強く存在します。
本記事では、画像・動画の生成AI利用において、企業が慎重になる理由と、WEB担当者が実務で押さえるべきポイントを整理します。
【商用利用の基本】AIが何を学習しているかを理解する
画像や動画の生成AIモデルは、インターネット上の膨大な画像データや、許諾を得たストック素材などを元に学習しています。そのため、表面的には“ゼロから生成”しているように見えても、既存の著作物の特徴を反映してしまう可能性があります。
ここで重要なのは、「商用利用OK」という表記だけでは安全性を判断できないという点です。モデルの学習データやライセンスによって企業利用の条件が変わるため、利用規約や権利情報に目を通しておくと、実務上の誤解を避けやすくなります。
企業が生成AI素材の利用を制限する主な理由
画像・動画生成AIは制作現場で急速に普及しつつある一方で、依然として利用に慎重な企業も少なくありません。その背景には、ビジュアル特有の権利リスクやブランド管理の難しさ、サービスごとに異なる規約への不安など、実務レベルで無視できない要因があります。ここでは、こうした“慎重姿勢”の土台となる理由を整理してみます。
1. 著作権・権利侵害のリスクが読みにくい
生成AIは、特定の写真家やイラストレーターの作風を思わせる表現を生み出すことがあります。
また、キャラクター・商品・建築物など有名なモチーフに似てしまうケースもあり、企業側としては、後から問題が発生する可能性をできるだけ排除したいという思いがあります。
2. サービスごとに商用利用ルールが違いすぎる
生成AIサービスは、商用利用の範囲や条件がサービスやプランごとに違うため、統一した基準では判断しにくい場面があります。たとえば、正式版では商用利用可能でも、ベータ版や無料プランでは制限が設けられることもあり、用途や契約内容によって扱いが変わります。
たとえば、Adobe(Adobe Firefly)は商用利用を前提に設計されており、企業向けに比較的安心して使えるライセンス体系を整えています。一方で、Midjourney(Midjourney Inc.)のように、有料プランに加入しなければ商用利用が認められないサービスも存在します。また、OpenAI(DALL·E 3)や ByteDance(Seedream 4.0)なども商用利用可能とされていますが、その条件や範囲はツールごとに異なります。
このように、「商用利用可」と一言でいっても、実際には“どのプランならよいのか”“どの範囲で利用できるのか”がサービスごとにバラバラであり、企業側が個別に判断・管理するには負荷が非常に大きくなります。
そのため、ルールが統一されていない段階では、企業として利用を制限せざるを得ないケースが少なくありません。
参考:
Adobe:https://www.adobe.com/legal/licenses-terms/adobe-gen-ai-user-guidelines.html
Midjourney:https://docs.midjourney.com/hc/en-us/articles/32083055291277-Terms-of-Service
OpenAI(DALL·E 3):https://openai.com/policies/row-terms-of-use/
ByteDance(Seedream 4.0):https://seed.bytedance.com/en/user-agreement
3. 自社素材がAIの学習に使われるのでは?という不安
製品写真、デザイン案、顧客データなど、社外に出せない情報を扱う企業では、「アップロードしたものがモデルの再学習に使われるのでは?」という不安が強く、生成AIの利用を初期段階で制限するケースが多く見られます。
実際には、企業向けプランでは入力データを学習に使わない方針を示すサービスも増えてきています。ただし、扱いはサービスごとに異なり、無料プランや一般向けプランでは学習に利用される場合もあるため、個別の利用規約を確認することが重要です。
そのため企業としては、「どのサービスの」「どのプランを」「どの用途で」使うかを明確に管理しない限り、機密データをアップロードすることに慎重になる、という状況があります。
4. 肖像権・パブリシティ権のリスク
人物画像や動画を生成する場合、意図せず実在の人物に似てしまうことがあります。特に、知名度のある芸能人やインフルエンサーに特徴が近づくと、本人の許諾なしに“似顔絵”を利用していると解釈される可能性があります。これが 肖像権・パブリシティ権の侵害につながるリスクです。
さらに、AIによる人物生成は、髪型・顔立ち・ポーズなどの組み合わせによって、偶然にも特定人物を連想させてしまうことがあり、企業としては「誰かに似ていないか」を客観的に判断することが難しい点も課題です。
加えて、SNS広告や動画コンテンツのように露出が広がる媒体では、第三者からの指摘につながりやすく、リスクが顕在化するスピードも早いという特徴があります。
こうした背景から、多くの企業は人物生成AIの利用には特に慎重であり、公式ビジュアルでは使用範囲を限定したり、完全に禁止したりするケースも見られます。
5. ブランド品質が担保できない
生成AIは高い表現力を持つ一方で、出力内容が常に安定しているわけではありません。人物の手や背景の形状が不自然になったり、衣服や質感が崩れたりといった“細部の破綻”が突然発生することがあります。また、同じプロンプトでも毎回異なる雰囲気のビジュアルが生成されるため、ブランドとして求められる統一感やトーン&マナーを維持しにくいという課題も残ります。
企業の公式サイトやキャンペーンビジュアルのように、“一度公開すればブランドイメージとして広く認知される”領域では、こうした細かな揺らぎが大きな問題となります。特に大企業の場合、ビジュアルガイドラインやCI/VIが厳密に定められているため、AI特有の曖昧な表現がブランドの文脈に合わないことも少なくありません。
そのため、AI生成画像を主要ビジュアルとして採用するには、品質チェックや修正作業が必須となり、結果的に従来より手間が増えてしまうケースもあるという現実があります。こうした理由から、ブランドを重視する企業ほど、生成AI素材の利用には慎重になりがちです。
6. AI倫理・バイアス問題への懸念
生成AIは、大量の学習データをもとに人物像やシーンを生成しますが、そのデータ自体に偏りが含まれている場合、特定の人種・性別・年齢層のステレオタイプを強化した表現が出力されることがあります。たとえば、特定の職業に男性だけが描かれる、肌の色や身体的特徴が極端に偏る、あるいは文化的に不適切な描写が紛れ込む、といったケースです。
企業にとって、こうした出力は ブランドイメージの毀損・社会的批判につながる可能性があり、特にグローバル市場や多様性を重視する領域では慎重な判断が求められます。さらに、AI生成プロセスの透明性が十分に説明できない場合、広報や法務の観点からも公開が難しくなることがあります。
ESG(環境・社会・ガバナンス)の観点では、企業が扱うコンテンツには社会的責任が求められます。そのため、“AIが生成したものだから仕方ない”では済まされないという認識が広がり、生成AI素材の利用を制限する企業が増えている状況です。
誰がどんな素材を作ったか、どこで使われたかを追跡できない状態では、トラブルが起きた際に対応が困難です。
そのため、ルール整備が進むまで利用制限するのは合理的判断といえます。
実務でよくあるグレーゾーン
生成AIによる画像・動画制作は、現場での利用機会が増えるにつれ、「このケースはどこまで許容されるのか」「商用利用として問題がないか」と迷う場面も多くなっています。とくにブランド表現や広告利用が絡む場合は、明確に正解が示しづらいため、プロジェクトごとに判断が分かれやすい領域が生まれています。ここでは、実務の中で迷いやすいケースを例として取り上げ、その判断が揺れやすい理由をまとめます。
LP・バナー画像にAIで生成したビジュアルを使ってよいのか?
LPやバナーは、企業が伝えたい情報を視覚的にまとめる役割が大きいため、AI生成画像を使用する際には、サービスの商用利用範囲や、生成物が既存作品と似ていないかといった確認が必要になる場合があります。抽象的な背景などでは扱いやすい場面もありますが、とくに広告出稿やキャンペーン用途ではより慎重なチェックが求められることもあり、企業によって判断が異なる部分です。
AI生成の背景と実写の商品写真を組み合わせてもよいのか?
背景をAIで生成し、商品写真と組み合わせる方法は増えていますが、背景の中に著名な建築物やアート作品を連想させる表現が含まれていないかなど、細部のチェックが必要になる場面があります。背景そのものが問題なく見えても、意図せず既存作品に近い描写が紛れ込むこともあるため、公開前に気になる箇所がないかチェックしておくとよいでしょう。
SNS動画でAI生成キャラクターを使うのは大丈夫か?
SNS動画は反応の速度が早く、視聴者の受け取り方もさまざまなため、AI生成キャラクターの使用には注意が向けられることがあります。実在人物と似ていると見なされる可能性や、SNSの特性上、予期せぬ拡散につながるリスクも考慮されるため、企業によっては使用範囲を限定するなど慎重に進めるケースもみられます。
動画生成AIで動きや構図を作るのは問題ないのか?
動画生成AIは、動きや構図が既存作品に近づいてしまうケースもあり、その点が判断を難しくすることがあります。商用利用として採用するには追加の調整や確認が必要となる場合もあります。一方で、企画段階のイメージ共有や方向性を検討する用途では、大いに有用であり、制作プロセスを効率化できる場面も多くあります。
参考画像をAIに読み込ませてテイストを似せるのは許容されるか?
制作のヒントとして参考画像を読み込ませ、雰囲気だけ近づける手法も広がっています。ただし、似すぎた表現にならないか、参考画像の権利状態がクリアか、といった点に気を配る必要があり、この領域については企業ごとに判断がばらつきやすい傾向があります。
オウンドメディアの挿絵やアイキャッチとしてAI画像を使うのは?
記事の挿絵やアイキャッチではAI画像が使われることも多いですが、人物を含むイラストやリアル表現の場合は、意図せぬバイアスや違和感が発生することもあります。リスクは比較的低いと考えられる一方、企業や媒体の方針によって扱いが異なるため、使用前に軽くチェックしておくと安心です。
全体として、生成AIの利用には便利さとともに曖昧なポイントも残っており、「使える/使えない」を単純に線引きしづらいケースが多くあります。最終的には、企業の方針、サービス規約、ブランドの方向性などを踏まえつつ、プロジェクトごとにバランスを取りながら進められることが重要です。
企業として整えることが望ましい「AI素材利用ガイドライン」
生成AIによる画像・動画の活用は、うまく使えば制作効率を高められる一方で、判断が難しい場面もあります。企業としては、今のうちに最低限の“考え方の整理”をしておくと、現場が迷いにくくなることがあります。
ここでは、その一例として、検討時に役立つポイントを簡単にまとめます。
利用するAIサービスの選び方を整理しておく
・商用利用の範囲が明確か
・著作権や権利の取り扱いが理解しやすいか
・学習データへの利用の有無が確認できるか
・利用ログやアカウント管理の仕組みがあるか
こうした観点を「チェック項目」として持っておくと、サービスごとの違いが把握しやすくなります。
生成物を使う前に、軽く確認する流れをつくる
厳しい審査体制を作る必要はありませんが、
・既存の作品に似ていないか
・利用範囲(広告・SNS・印刷など)が社内ルールに合っているか
といった 簡単な確認ステップ を設けておくと、後からのトラブルを避けやすくなります。
入力データやプロンプトの扱いを明確にしておく
顧客情報や未公開の素材をAIに入力するかどうか、「どのサービスなら入れて良い/避ける」などの方針をゆるやかに決めておくと安心です。必ずしも厳密に管理する必要はありませんが、判断基準が共有されているだけで混乱を減らせます。
外部パートナーとの認識を合わせておく
制作会社や代理店がAIを使う場合、
・どこまで利用して良いか
・生成物の権利はどう扱うか
といった点について、制作前に認識をあわせておくと、双方が安心して進めやすくなります。
まとめ
企業が生成AI素材の利用に慎重になる背景には、著作権や肖像権、ブランド品質といった領域で“どこまで安全と言えるか”を判断しづらい現実があります。現時点ではリスク管理の情報が整理しきれておらず、その結果として利用が限定されている側面があるといえます。
しかし、仕組みを整えながら少しずつ活用範囲を見極めていけば、生成AIは制作の幅を広げたり、業務のスピードを高めたりと、十分に役立つ場面が増えていく可能性があります。大事なのは、無理に全面活用することではなく、各企業の状況に合わせて扱いやすいところから取り入れていく姿勢です。
WEB担当者が基礎的な知識を押さえ、社内外に分かりやすく説明できるようになることで、企業としても“安全に活用できる体制を整える”という次のステップに進みやすくなります。生成AIは、適切に向き合えば、制作・運用の新しい選択肢として機能していくはずです。
関連記事
-

WEBサイト運用に潜む構造的な課題と、今見直すべき体制・プロセス
WEBサイト運用に潜む構造的な課題を整理し、体制・情報管理・技術基盤・セキュリティの観点から、安定した運用を行うための見直しポイントを解説します。
2025.11.23 #WEB・広報担当者のための基礎知識 -

WEB担当者のためのタイのPDPA(個人情報保護法)対応ガイド
タイの個人情報保護法PDPAをわかりやすく解説。フォームやCookie、プライバシーポリシーなどWEB担当者が押さえるべき対応ポイントを整理します。
2025.11.09 #WEBサイト制作#WEB・広報担当者のための基礎知識 -

ストックフォトサービスのライセンスとは 〜企業サイトで安全に画像を使うための基礎知識〜
2025.11.01 #WEB・広報担当者のための基礎知識