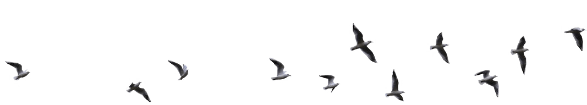WEBサイトでGoogle Mapを使うときの著作権ルールをやさしく解説

企業や店舗のWEBサイトに所在地を掲載する際、多くの方が「Google Mapを使いたい」と考えるのではないでしょうか。直感的にわかりやすく、利用者にとっても便利な地図サービスですが、その一方で「著作権はどうなっているのか」「商用利用は問題ないか」と不安の声を耳にすることがあります。
実際、地図や航空写真といったコンテンツも写真やイラストと同様に著作権の対象となるため、利用方法を誤ると規約違反やトラブルにつながる可能性があります。しかし、基本的なルールを理解して正しい方法で利用すれば、安心して自社のWEBサイトに活用することができます。
Google MapをWEBサイトに掲載する際に押さえておきたい著作権の考え方と、安全に利用するためのポイントを、専門知識のない方にもわかりやすく解説していきます。
Google Mapの著作権とは
まず前提として、地図そのものが著作権法における「著作物」として保護されています。地図は単に場所を示すだけの記号の集まりではなく、情報の選び方や表現方法に作成者の工夫や意図が反映されています。そのため、写真やイラスト、文章と同様に創作性を持つ著作物と見なされ、無断利用や改変は著作権侵害につながる可能性があります。
Google Mapも例外ではありません。地図表示や航空写真、ストリートビューの映像はすべて著作権の対象であり、Googleが独自に制作したものだけでなく、ゼンリンなどの外部提供元からライセンスを受けて提供しているデータも含まれています。つまり、自由にコピーしたりスクリーンショットを加工して利用したりすることは、著作権侵害や利用規約違反に該当する恐れがあるのです。
重要なのは、「Google Mapだから特別に自由に使える」のではなく、地図という表現物自体に著作権があるという理解です。そのうえで、Googleが公式に認める利用方法を選択することで、安全にサイトへ組み込むことができます。
Google Mapを安心して利用できる方法
Google MapをWEBサイトで安全に利用するためには、Googleが定めるルールに沿った方法を選ぶことが大切です。以下の方法を押さえておけば、著作権や規約違反を心配する必要はありません。
埋め込み機能を利用する
最も手軽で一般的なのが、Google Mapに用意されている「埋め込みコード」を使う方法です。地図画面の「共有」メニューから発行されるコードを自社サイトに貼り付けることで、Googleが提供する正規の形で地図を表示できます。特別な契約や設定は不要で、ほとんどの企業サイトに適した方法といえます。
スクリーンショットは避ける
「地図をキャプチャして画像として掲載する」という方法は便利に思えますが、これは規約違反になる可能性があります。特に商用サイトではリスクが高いため、原則として避けるべきです。やむを得ず画像で扱う場合は、地図(Map表示)に限りスクリーンショット利用が可能です。その際は、画面内の帰属表示を残し、コンテンツの近くに可読状態で掲示し、UIや色など見た目を大きく変えないことが必要です。Street Viewはスクリーンショット不可で、埋め込みやAPIのみ許可されます。
また、帰属の表記は画像や地図の近くで読める大きさで掲示します。フッター等へ分離移動は不可。表示される第三者データ提供者名も省略せず含めます。
Google Map Platform(API)の活用
自社サイトで複数拠点のピン表示やルート検索、カスタムデザインの地図など、より高度な機能を実装したい場合には「Google Map Platform(API)」を利用するのが適切です。
このサービスは、Googleが公式に提供している開発者向けの仕組みで、地図データや機能を自社サイトやアプリに組み込めるように設計されています。利用にはGoogleアカウントの登録とAPIキーの発行が必要です。
料金体系は「利用量に応じた従量課金制」になっており、基本的にリクエスト数(=地図を表示した回数や利用した機能の回数)に応じて費用が発生します。ただし、Googleは毎月一定額(200ドル分)の無料枠を提供しており、小規模な利用であれば無料範囲内に収まるケースも少なくありません。
重要なのは「正式にライセンスを得た形で利用できる」という点です。APIを使えばスクリーンショットや不正利用のリスクを避けつつ、必要に応じて自由度の高いカスタマイズが可能になります。企業サイトでの地図利用を本格的に検討する場合には、まずこの方法を選ぶのが安心です。
Googleが提供する「埋め込み機能」や「Google Map Platform(API)」を正しく利用すれば、企業サイトなど商用利用であっても問題ありません。収益目的の機能統合や高度なカスタマイズを行う場合はGoogle Maps Platform(API)を利用してください。
参照元:Google社「Google マップ、Google Earth」
https://www.google.com/intl/ja/permissions/geoguidelines/
Google Mapの利用時に気をつけたい表示ルール
Google Mapを正しく埋め込んだり、APIを通じて利用する場合でも、守らなければならない表示上のルールがあります。これらは著作権や利用規約に関わる重要なポイントですので、必ず押さえておきましょう。
クレジット表記を消さない
地図の右下には「Google」や「Map data ©●●」といったクレジット表記が自動的に表示されます。これは著作権者を明示するために必要な表示であり、削除や隠蔽をしてはいけません。見た目を整えたいからといってCSSなどで非表示にするのは規約違反となります。
地図の表示を妨げない
広告バナーや他の画像で地図の一部を覆ってしまうと、利用者にとって見づらくなるだけでなく、利用規約に抵触する場合があります。地図が正しく表示されるよう、配置やレイアウトには注意しましょう。
表示の改変を行わない
Google Mapのスクリーンショットを加工して色を変えたり、一部を切り取って使うことはできません。公式の埋め込みやAPIで提供される形そのままを利用することが基本です。デザインを自社サイトに合わせたい場合は、Google Map Platformのカスタマイズ機能を活用しましょう。
もし間違った使い方をするとどうなる?
Google Mapを正しく利用せず、スクリーンショットの掲載やクレジットの削除など規約に反する方法をとった場合、いくつかのリスクが考えられます。
利用停止や削除要請を受ける可能性
まず考えられるのは、Googleや権利者から「利用をやめてください」と指摘されるケースです。著作権や規約に違反している場合、該当ページの修正や削除を求められることがあります。
信用の失墜につながる
企業の公式サイトで不適切にGoogle Mapを利用していることが発覚すると、単なる規約違反にとどまらず、社会的信用の失墜につながる可能性があります。著作権や利用規約を軽視していると見なされれば、顧客や取引先からの信頼を損ない、ブランドイメージにも深刻な影響を及ぼしかねません。
実際に、ある自治体の公式ホームページで、地図情報提供者の利用規約に反する形で地図を掲載していた事例があります。このケースでは、国土地理院やGoogle Mapなどが提供する地図を自治体サイトに掲載する際、出典表示の不備や地図の扱い方において提供元の利用規約に反する可能性があると指摘されました。その結果、数千件に及ぶページの削除や差し替えが必要となり、対応に追われる事態となったのです。
このような事例は報道によって広く知られることもあり、公的機関であっても著作権や規約に違反すれば社会的批判を受けるという事実が明らかになりました。企業においても同様で、一度損なわれた信用を回復するには長い時間と大きなコストを要する可能性があります。
法的リスクに発展する場合も
悪質な利用や無断加工を続けた場合、著作権侵害として法的措置をとられることも考えられます。特に商用利用では、損害賠償請求といったリスクに発展するケースもゼロではありません。
まとめ
Google Mapは利便性が高く、多くのWEBサイトで活用されていますが、著作権や利用規約を無視した使い方をすると、思わぬトラブルや社会的信用の失墜につながる恐れがあります。
安心して利用するための基本は、「埋め込み機能を使う」か「Google Map Platform(API)を利用する」という2つの正規ルートを押さえることです。そして、クレジット表記を消さない、改変しない、といった表示ルールを守ることも欠かせません。
こうしたポイントを理解しておけば、著作権のリスクを回避しながら、自社サイトの利便性を高めることができます。もし判断に迷う場合は、制作会社や専門家に相談するのも有効です。正しい知識を持ち、安心してGoogle Mapを活用することが、企業の信頼性を守る第一歩となるでしょう。