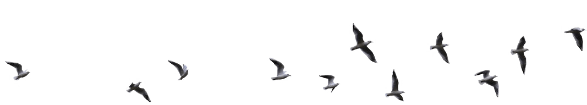採用ブランディングにおけるコーポレートサイトの役割 ー タイ日系企業がタイ人求職者に「選ばれる会社」になるために
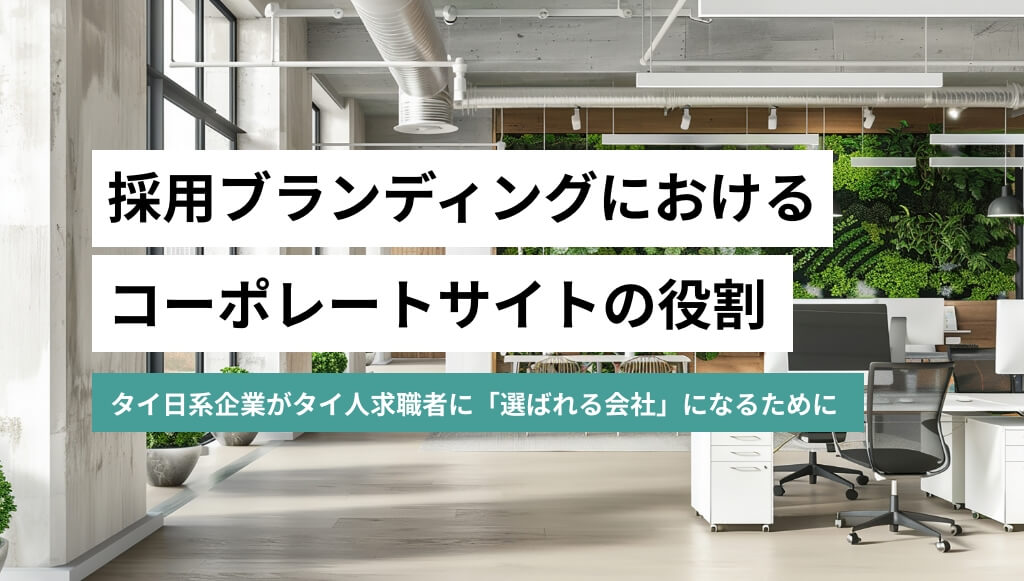
近年、タイの採用市場は大きく変化しています。
給与や福利厚生といった条件面だけでは、優秀な人材の関心を引くことが難しくなりつつあります。とくに日系企業においては、「日系だから」といった従来のイメージだけでは十分に響かない場面が増えています。
近年の求職者は、どんな人が働いていて、どんな価値観を大切にしている会社なのかを意識する傾向が強まっています。
こうした変化の中で、コーポレートサイトは企業の人格や文化を感じてもらうための場として、ますます重要性を増しています。企業の考え方や日々の取り組みを通じて共感を育てる大切なタッチポイントになりつつあります。
この記事では、採用ブランディングの考え方を踏まえながら、コーポレートサイトがどのように信頼・共感・行動を生み出し、企業全体の採用力を高めていけるのかを考えていきます。
タイ市場における採用ブランディングの重要性
「求人を出しても応募が思うように集まらない」
「面接まで進んでも辞退されてしまうことが多い」
そんな課題を感じている企業も多いのではないでしょうか。
多くのケースで、問題は条件や待遇そのものよりも、“企業の魅力が求職者に十分伝わっていない”ことにあるようです。その重要性は理解されていても、実際には十分に取り組めていない企業が少なくありません。
いま求められているのは、求職者に向けて自社の価値や文化を伝え、共感を育てていく「採用ブランディング」という視点です。
採用ブランディングとは、自社がどんな会社で、どんな想いを持って人と向き合っているかを伝えること。
言い換えれば、「この会社で働く意味」を、候補者に理解してもらうための活動です。
タイの採用市場では、優秀な人材ほど転職サイクルが短く、条件だけでは選ばれにくくなっています。
求人票には書ききれない“企業で働くイメージ”が見えないと、候補者の記憶に残らず、他社との比較の中で埋もれてしまいます。採用ブランディングは、そうした情報の空白を埋め、企業の文化や人の魅力を言語化して伝える取り組みです。
商品ブランドが顧客との信頼を築くように、採用ブランドは未来の社員との信頼を築きます。理念や価値観、働く人の姿を通して「この会社となら成長できそうだ」と思ってもらう。その積み重ねが、長期的な採用力につながります。
特にタイでは、若い世代ほど給与や肩書きよりも、職場の雰囲気や人間関係、価値観の合う環境を重視する傾向があります。一方で、日本企業には「意思決定が遅い」「意見が言いづらい」といった印象を持たれることも少なくありません。現地のスタッフが「自分の考えを尊重してほしい」と感じる背景には、文化的なギャップがあります。
だからこそ、日系企業は“日本らしい誠実さ”を大切にしながら、“現地らしい開かれた文化”をどう見せるかが重要です。採用ブランディングとは、そのバランスを形にし、「ここで働きたい」と思われる理由をつくる取り組みなのです。

“気になる”から“共感”へ。サイトは、企業の想いが伝わる最初の接点。
面接前に「会社の中身」を伝え「意欲を育てる」採用へ
タイの日系企業の多くは、人材紹介会社や求人ポータル(JobDB、JobThai、LinkedInなど)を中心に採用活動を展開しています。これらの外部チャネルは応募獲得において欠かせない存在ですが、企業独自の価値観や働く魅力を発信するフェーズが後回しになっていることも少なくありません。
採用面接を控えた求職者の多くは、まず企業の公式サイトを開き、その企業がどんな事業をしているのか、どんな人が働いているのか、自分に合う職場なのかを確かめます。そこで受ける印象が、その企業に対する信頼や興味を大きく左右します。
多くの日系企業は、人材紹介会社や求人ポータルを通じて一定の応募を得ていますが、その後に企業の価値観や文化を伝えきれず、条件面だけで選ばれてしまうケースが少なくありません。応募数を追うだけでは、本当の意味での“選ばれる採用”にはつながらないのです。
本来の採用ブランディングとは、応募を集めることに加え、企業の価値観や人の魅力を自らの言葉で伝え、共感を得ることにあります。その役割を果たせる唯一の場所が、コーポレートサイトです。企業の想いや文化を伝える場を自社の中に持つことが、長く愛される採用ブランドを育てる第一歩になります。
コーポレートサイトが果たす3つの採用ブランディング機能
企業にとって求人媒体やSNSは求職者の「認知を広げる場」ですが、コーポレートサイトは「理解と信頼を深める場」です。求職者はコーポレートサイトを訪れ、会社の理念や雰囲気、働く人の姿を通して「自分に合うかどうか」を判断します。つまり、コーポレートサイトは単なる会社紹介ではなく、“企業の人格”を伝えるメディアとして機能するのです。
その中で特に重要な役割を果たすのが、次の3つの視点です。
①「信頼」を生む ― 企業の姿勢を見せる場
会社概要や代表メッセージ、CSR活動、実績といった情報は、求職者にとって「この会社は信頼できるか」を見極める手がかりになります。
特にタイでは、企業の安定性も重視されますが、それだけでは決め手になりません。「どんな姿勢で事業に取り組んでいるか」「社員をどのように大切にしているか」に加えて、「どんな人たちと働くのか」「職場にどんな雰囲気があるのか」といった“人の温度”を感じられる情報に関心を持つ人が増えています。
業績や沿革といった基本情報ももちろん大切ですが、それだけでは伝わりにくい“企業の中にある想い”があります。経営者がどんな考えで会社をつくり、どんな社会的価値をめざしているのか。そして、その考え方が現場でどのように受け継がれ、日々の仕事や人の関係性にどう息づいているのか。そうしたストーリーを自社の言葉で語ることが、企業としての「姿勢」を伝えることにつながります。
コーポレートサイトは、数字や制度だけでは伝わりにくい“その企業らしさ”を感じてもらえる場といえるでしょう。形式的な会社紹介にとどまらず、「この会社にはどんな想いがあり、どんな人が働いているのか」を丁寧に伝えることで、少しずつ信頼を築いていくことにつながります。
②「共感」を育てる ― 働く人のリアリティを伝える場
企業の文化や雰囲気は、理念や言葉よりも“働く人の姿”を通してこそ伝わります。
社員紹介やインタビュー、1日の仕事の流れ、社内イベントの様子など、日常のリアルな情報は、見る人の共感を引き出します。
写真や動画の印象も大切です。過度に整えられたものよりも、実際の職場や社員の自然な表情が伝わる素材の方が、見る人に安心感を与えます。
その中で伝えたいのは、単なる職場紹介ではなく「この会社で働くからこそ得られる経験や成長の機会」です。
求職者が自分の将来を重ねられるようなストーリーがあれば、「この会社で働いてみたい」という気持ちは自然に育っていきます。
見る人が心を動かされるのは、企業が語るメッセージよりも、現場で働く人の声や表情にふれた瞬間かもしれません。コーポレートサイトでそうした瞬間を丁寧に設計することが、共感を育てるための第一歩になります。
③「行動」を促す ― 求職者を採用サイトへ導く導線設計
コーポレートサイトには、取引先や顧客、採用候補者など、さまざまな立場の人が訪れます。
その中には、求人サイトや人材紹介会社を通じて企業を知り、「どんな会社なのか」を確かめに来る求職者も少なくありません。
だからこそ、事業やサービスの紹介ページの中にも、“働く人”や“企業の考え方”に自然につながる導線を設けておくことが大切です。
求職者が企業の姿勢に共感し、「もう少し知りたい」と思ったときに、迷わず採用関連の情報へ進める構成が理想的です。
コーポレートサイト全体を通じて、求職者が「この会社と関わりたい」と感じる流れをデザインすることが、信頼と行動を生む基盤になります。

採用ブランディングにおいては、コーポレートサイトの訴求力が鍵となります。
タイ日系企業が抱える課題と改善のヒント
多くのタイ日系企業では、採用活動自体は行われているものの、「自社の魅力をどう見せ、どう伝えるか」という視点が十分に整理しきれていないケースも見られます。せっかくの強みやブランド力を持ちながらも、それをどう伝えるかに悩む企業も多いようです。
ここでは、タイの日系企業でよく見られる4つの課題と、その改善の方向性を整理します。
1. コーポレートサイトを「今の姿」にアップデートする
10年以上更新されていなかったり、スマートフォン非対応のままになっている企業も少なくありません。
これは特に若い世代の求職者にとって「情報が古い=企業も古い」という印象につながり、信頼を損ねる要因になります。
まずは、デザインや情報構造をモバイル基準で再設計し、UI・UXの改善を行うことが第一歩です。
新しいサイトはそれ自体が「今も進化している企業」であることの証明になります。
2. 採用情報を一元化し、メッセージを統一する
求人媒体ごとに内容や表現が異なり、トーンや情報が統一されていないケースが多く見られます。
この状態では、企業としてのメッセージが伝わりにくく、求職者に混乱を与えかねません。
自社サイトに採用関連情報を集約し、一貫した言葉で発信することが信頼形成の基本です。
外部媒体とは連携しつつも、「なぜこの会社で働くのか」「どんな人と共に成長できるのか」を自社の言葉で語ることが大切です。
3. 働く人や社風を可視化し、共感を生む発信を
タイ人スタッフがどんな環境で働き、どんな雰囲気の職場なのか――そうした“日常のリアリティ”が外から見えない企業は少なくありません。
求職者が知りたいのは、制度よりも**「どんな人と働けるか」「どんな空気の職場か」**という部分です。
写真や動画、社員インタビューなどを活用し、リアルな“働く人”を伝えることで共感が生まれます。
派手な演出よりも、自然な笑顔や本音の言葉のほうが、はるかに信頼感を与えます。
4. 理念や想いを、伝わる言葉でローカライズする
経営理念や企業メッセージが日本語だけで掲載されていたり、形式的な文章のままになっているケースも目立ちます。
タイ人の求職者に届く言葉で理念を伝えるには、タイ語や英語での再表現が欠かせません。
完璧な翻訳でなくても、「なぜこの仕事をしているのか」「どんな価値を社会に届けたいのか」をローカル言語で語ることが、企業の本気度を伝えます。
これらの課題はいずれも、大規模な投資や特別なキャンペーンを必要とするものではありません。
むしろ、現地の声を取り入れ、日常的に発信を続けることが最も効果的です。
たとえば、月に1本でも現地スタッフのインタビューを追加する、CSR活動や社内イベントを写真付きで紹介する。
そんな小さな積み重ねが、「この会社は誠実で、信頼できる」という印象を育てていきます。
採用ブランディングとは、特別なプロジェクトではなく、企業の日常を丁寧に見せることから始まります。現地の人々が共感し、自分の未来を重ねられるような発信を続けることが、タイ市場で“選ばれる企業”への確かな一歩です。
まとめ
タイの採用市場では、給与や待遇だけでなく、企業の価値観や働く人の姿が重視されるようになっています。
コーポレートサイトは今や営業や広報だけでなく、採用の中核を担う存在です。理念や事業の方向性、働く人のリアルな姿を通じて、企業の姿勢を伝える場となっています。
採用ブランディングで重要なのは、企業の魅力を一度に伝えることではなく、さまざまな接点で少しずつ理解と共感を深めてもらうことです。
コーポレートサイトを起点に、求人広告やSNSなどの発信を一貫させることで、「この会社と関わってみたい」という気持ちが自然に育ちます。
企業の“内面”をどう見せるかを意識し、コーポレートサイトをブランドの核として発信を重ねていくこと。
その積み重ねこそが、タイ市場で「この会社で働きたい」と思ってもらえる採用力につながります。
関連記事
-

【BtoB企業向け】WEBブランディングの基本と気をつけるべきポイント
BtoB企業におけるWEBブランディングの基本と、実務の中で気をつけるべきポイントを、わかりやすくご紹介します。
2025.07.02 #BtoBマーケティング#デジタルマーケティング -

タイで失敗しないためのWEBブランディングとは?現地で信頼と共感を得るための5つの視点
タイ市場では、製品の魅力に加え、企業の“姿勢”や“ストーリー”への共感がブランド選定の鍵となっています。タイでWEBブランディングを任された初心者の方に向けて、信頼と共感を得るための5つの視点をわかりやすく解説します。
2025.07.02 #デジタルマーケティング