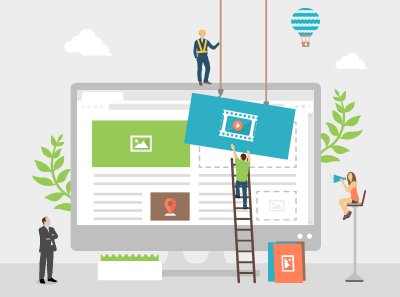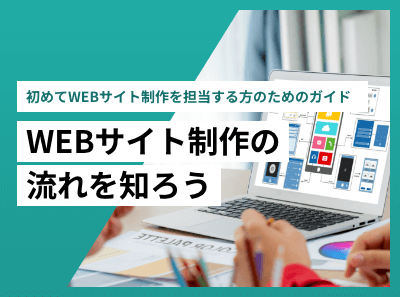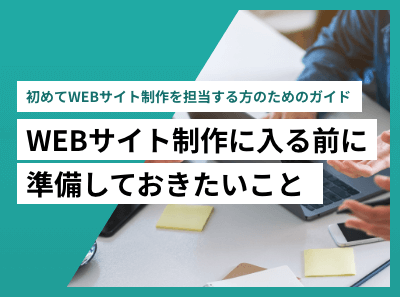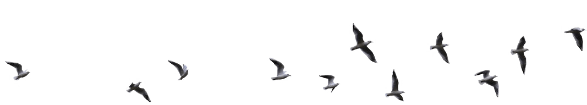HTMLの品質がWEBサイトの成果を左右する?初心者でもできる品質チェックの基礎知識
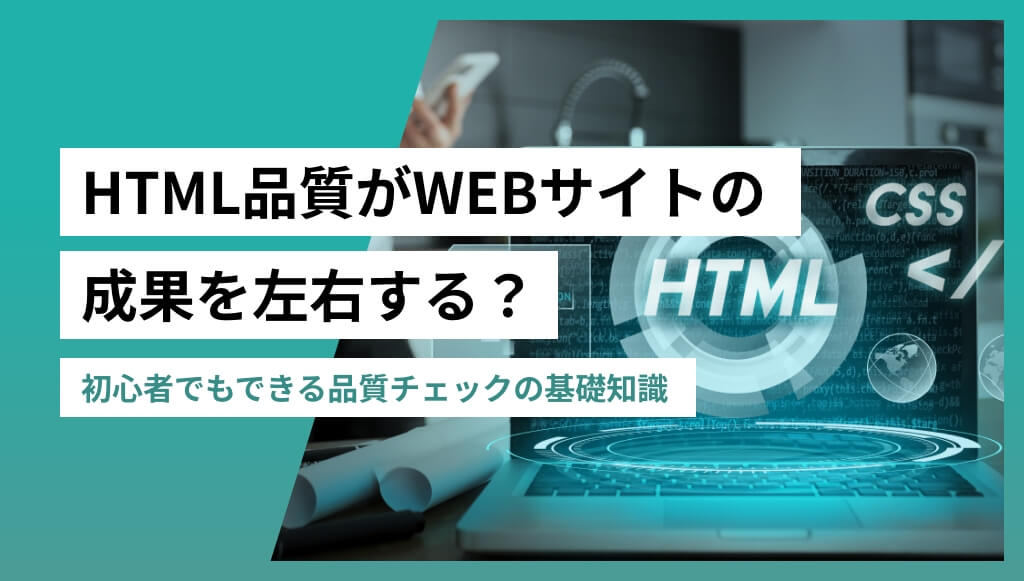
WEBサイト制作を検討していると「HTML」という言葉を必ず耳にします。しかし、実際にそれが何を意味するのか、そして良し悪しがどのように成果に影響するのかは、専門知識がなければ見分けがつきにくいものです。特にタイでは制作者ごとに品質の差が大きい反面、外からはなかなか良し悪しの判断がつきづらいものです。本記事では、「HTMLとは何か」から解説し、良いHTMLとそうでないHTMLの違いを見抜くための基本ポイントをお伝えします。
そもそもHTMLって何?
HTMLは「HyperText Markup Language(ハイパーテキスト・マークアップ・ランゲージ)」の略で、1990年代のはじめにインターネット上で文書をつなげて読むために作られました。スイスの研究機関CERNにいたティム・バーナーズ=リー氏が開発し、これが現在の「World Wide Web(WWW)」の出発点になりました。
従来の紙の本や資料はページを順番に読むものでしたが、ハイパーテキストはリンクをクリックして別の文書へ飛べる仕組みを持っています。これが「ハイパーリンク」で、いま私たちが当たり前に使っている“リンクをクリックして別のページに移動する”体験の原型です。
最初のHTMLはとてもシンプルで、見出しや段落、リンクくらいしか表現できませんでした。その後、表や画像を扱えるようになり、CSSやJavaScriptと組み合わせることで、今日のようなリッチなWEBサイトが作れるようになりました。
HTML:情報の骨組み
CSS:デザインや装飾
JavaScript:動きやインタラクション
この三位一体で、いまのWEBが成り立っています。
HTMLはインターネットと同じ歴史を歩んできた基礎技術です。つまり、どんなに最新のデザインやシステムを使っても、土台はHTML。なりたちを軽く知っておくだけでも「なぜ品質が大事なのか」が理解しやすくなり、制作会社に任せるときも納得感を持って判断できるようになります。
“良いHTML”に求められる5つの要素
WEBサイトは見た目がきれいでも、裏側のHTMLの書き方が雑だと、検索に弱かったり、使いにくかったり、修正しにくいサイトになってしまいます。では「良いHTML」とは、どんな特徴を持っているのかを押さえる基本ポイントを5つにまとめました。
1. 意味のある構造になっていること(セマンティクス)
WEBページは、人だけでなくブラウザや検索エンジン、読み上げソフトも読みます。彼らに内容を正しく伝えるには、ページの中で「ここは題名」「ここは章の見出し」「ここは本文」「ここは別ページへの案内」という役割がはっきりしていることが大切です。
その役割を機械にも分かる形で示すために、文章の一部に小さな“目印”を付けます。これがHTMLでいうタグ(印)です。たとえばページの題名には最上位の見出しの印(h1)、続く章には一段下の見出しの印(h2/h3)、本文には段落の印(p)、案内にはリンクの印(a)を付けていきます。
見た目だけ大きな文字にして「見出しっぽく」見せても、印が付いていなければ機械には意味が伝わらず、検索評価が下がったり、読み上げ順が不自然になったりします。
大事なのは、デザインを当てる前に情報の骨組みを決め、その骨組みに沿って印を付けていくことです。構造が整ったページは、検索にも強く、スマホでも読みやすく、将来の更新や増築もスムーズに進みます。初期設計での進め方は、下の関連記事で実務手順とあわせて解説しています。
2. 誰でも使いやすいこと(アクセシビリティ)
WEBサイトの使いやすさ(アクセシビリティ)とは、年齢や障害の有無、端末や通信環境の違いにかかわらず、誰もがそのサイトにたどり着き、内容を理解し、問題なく操作できる状態のことです。HTMLで情報の役割を明確にし、見え方と動き方を整える“基本品質”と言えます。
まず前提として、前述の構造化が適切に反映されている必要があります。ページの題名や章立て、本文、リンクといった役割がHTML上でも正しく示されていることが、読み手にも機械にも意味を伝える土台になります。
そのうえで、例えば、画像の扱いもアクセシビリティに大きく影響します。WEBページを読むのは人だけではなく、検索エンジンや読み上げソフトなどの機械も読みますし、通信状況や端末設定によっては画像が表示されないこともあります。そこで代替テキスト(alt属性)を活用し、画像の内容や目的を短く伝える説明をaltタグに加えることで、画像が表示できない状況や読み上げ時に意味を届けます。文字を画像化した見出しやボタン、製品写真や図、機能を示すアイコンのように意味を持つ画像には、要点がわかる短い説明を付けます。そもそも文字はできるだけ画像にせず、ふつうのテキストとして実装するほうが、読み上げにも検索にも確実です。
つまり、情報の“意味”をきちんと理解し、それを正しくコードへ落とし込めるかどうかが、コーダーのスキルの本質といえます。
3. 表示の速さ(パフォーマンス)
WEBサイトの表示速度は、読者が「読むか・離れるか」を決める実務的な品質といえます。表示速度はサーバーや回線状況、画像の作り方などHTML以外の要因にも左右されますが、HTMLのコードの組み方が大きく影響するものでもあります。
表示の速いページのHTMLは、ひと言でいえば「ブラウザに余計な迷いを与えず、必要な情報を先に、わかりやすく渡す」書き方になっています。骨組み(見出し・本文・リンク)がすっきり整理され、意味のない入れ子や装飾に引っ張られません。テキストはテキストとして提供され、画像や装飾に過度に依存しないため、読み始めるまでの障壁が少なくなります。読む順序(何を先に見せるか)も無理がなく、ページ全体が“軽やかに”進む設計です。
こうした作りは、スマートフォンの不安定な環境でも「すぐ読める」体験につながり、離脱の抑制やお問い合わせ率の改善に寄与します。
4. 検索に強いこと(SEOの基盤)
検索に強いことは、HTMLの品質を決める大切なポイントのひとつです。SEO対策と聞くと特別な対策を思い浮かべがちですが、実際には内部要因と呼ばれる、ページそのものの作りが土台になります。
検索エンジンはデザインや雰囲気を見るのではなく、HTMLの構造や意味づけを手がかりに内容を理解します。したがって、前述の「1 意味のある構造(セマンティクス)」「2 誰でも使いやすいこと(アクセシビリティ)」「3 表示の速さ(パフォーマンス)」が整っていることで、そのページは検索エンジンにとっても理解しやすくなるといえます。
逆に、構造が曖昧だったり、画像任せのデザイン、表示が遅くユーザーがすぐ離れてしまうようでは、検索結果で評価されにくくなります。つまり「検索に強いHTML」とは、見た目を整えること以上に、情報の意味をきちんと伝える品質あるコードが書かれているかどうかで決まるのです。
検索エンジンが求める品質について詳しく知りたい方は以下の記事もご参照ください。
5. 更新のしやすさ(保守性)
HTMLの品質を語るうえで、「更新のしやすさ」は長期的にWEBサイトを運用していく企業にとって非常に重要な視点です。初期公開時には見えにくいものの、日々の更新や改修、担当者の入れ替わりがあったときに差がはっきり現れます。
整ったHTMLは、見出し・段落・ボタンなどの要素ごとに役割が整理され、共通部分は共通のコードで書かれています。たとえば同じ種類の見出しなら常に同じタグとクラスが使われ、ボタンもデザインや動きが揃っています。ルールが全体で統一されているので、後から加わった人でも「ここはこの書き方をすればいい」とすぐに理解でき、修正や追加が短時間で済みます。
逆に、場当たり的に書かれたHTMLは一見すると動いていても、中身はバラバラです。同じ見出しがページごとに違うタグやスタイルで書かれていたり、急場しのぎのプラグインが積み重なっていたりすると、どこを直せばいいのか把握するのに時間がかかります。ほんの一文の差し替えでも他の部分に影響が出てしまい、更新のたびにコストやリスクが増えてしまうのです。新しい担当者が引き継ぐときにも、コードが整理されていなければ理解に時間がかかり、思わぬ不具合を生みやすくなります。
多言語ページの追加やキャンペーン用ランディングページの量産、あるいは構成そのものを入れ替えるといった拡張に強いかどうかは、HTMLの整理度合いで決まります。全体に共通したルールで書かれ、読みやすく再利用しやすいコードは、企業にとって長期的に価値を持つものになります。逆にぐちゃぐちゃのコードは、見えないところで運用負荷とリスクを積み上げてしまいます。
つまり、きれいに書かれたHTMLは単なる「見た目の裏側」ではなく、将来にわたって企業の活動を支える大切な資産となるのです。

整理されたHTMLは、メンテナンス性や信頼性を高め、コスト削減や競争力向上につながる“企業の資産”となりえます。
HTMLコーディングのよくある失敗事例
WEBサイト制作は一見するとどれも同じように見えますが、裏側のHTMLには品質の差があり、それが成果に直結することも少なくありません。特に専門知識がないと、見た目が整っていることで安心してしまいがちですが、内部の作りに問題があると集客や運用で思わぬ不利益を招くことがあります。ここでは、一般的に制作現場でしばしば見られる失敗例を取り上げてみます。
1. 見出しタグが装飾目的で乱用されている
本来、<h1>や<h2>といった見出しタグは、ページの骨組みを示すためのものです。しかし中には、単に文字を大きく見せたいからという理由で乱用されているケースが少なくありません。デザイン的には大きな文字で目立っていても、構造としては「見出し」としての意味を持たないため、検索エンジンはページ全体の内容や階層を正しく理解できず、結果的にSEOの評価を下げてしまいます。
さらに乱用どころか「そもそも見出しタグ自体が入っていない」というケースも多々見られます。すべての文字が段落タグや装飾用のタグで書かれていると、機械から見るとページは“見出しのない長文の塊”になり、内容の整理が伝わりません。検索エンジンだけでなく、スクリーンリーダーを使うユーザーにとっても「どこからどこまでが章のまとまりなのか」が把握できず、読みづらい体験になります。
見出しタグは見た目の大きさを決めるためのものではなく、情報の階層と流れを示すためのラベルです。正しく使われていれば、検索エンジンにもユーザーにも「何が大事で、どういう順番で読むべきか」が伝わります。
2. テンプレートを流用しただけで中身が整理されていない
タイ現地の制作会社の中には、海外製のテンプレートをそのまま流用し、不要なコードや使われていないスクリプトを残したまま納品するケースが見られます。市販や海外製のテンプレートをベースに制作すること自体は、短納期・低コストを実現する手段として有効です。ただし、導入時に不要なコードや使われていないスクリプトが整理されないまま残っていると、見た目は問題なくても、内部では余計な処理が積み重なってしまいます。
初期段階では問題が表面化しなくても、時間が経つにつれて影響が出やすくなります。例えば、更新や機能追加をしたときに思わぬ不具合が起きたり、読み込みが重くなって表示速度に影響したり、新しい担当者がコードを理解しにくく作業が滞る、といったリスクです。結果として、当初は安価に見えた制作費用が、長期的には修正や手戻りのコストで膨らんでしまうこともあります。
テンプレート自体の利用は効率化の手段として有効です。ただ大切なのは、実際の運用に合わせて不要な部分を整理し、ルールを整えた状態で納品されているかという点です。整理されたコードであれば、保守や拡張がスムーズに行え、結果的に長く安心して使える資産となります。
3. プラグイン多用によるコードの乱雑化
WordPressなどのCMSを使う場合、本来は必要最小限のプラグインで設計するのが理想です。しかし実際には「短期間で安く構築する」ことを優先し、多数のプラグインを組み合わせてサイトを仕上げるケースも少なくありません。見た目は問題なく動いていても、内部では不要なHTMLタグやCSS・JavaScriptが大量に出力され、コードが複雑化してしまいます。
このような状態では、ページのソースに似たようなコードが何重にも記述されていたり、実際には使われていないスクリプトやスタイルが読み込まれていたりします。その結果、表示速度が遅くなり、ユーザー体験が損なわれるだけでなく、SEOの評価にも影響します。
また、プラグインを多く抱えすぎると、セキュリティ面での注意も必要になります。プラグインは開発元によって更新頻度や品質に差があり、古いものを放置していると脆弱性を突かれるリスクが高まります。数が増えるほど管理が複雑になり、アップデートや監視が行き届きにくくなる点も見逃せません。
さらに、保守性の低下も大きな課題です。ちょっとした機能追加の際にプラグイン同士の相性問題でエラーが出たり、修正に余計な工数やコストがかかることも珍しくありません。
プラグインの利用そのものは悪いことではなく、適切に選べば大きな効率化につながります。大切なのは、必要な機能を見極めて最小限にとどめ、整理された状態で運用することです。そうすれば表示速度やセキュリティの不安を抑えながら、長期的に安心して使えるサイトへと育てることができます。
WEBサイト制作にノーコードツールを使用するメリット・デメリットについて知りたい方は以下の記事もご参照ください。
こんなケースは要注意
自社のWEBサイトをチェックしての、次のような現象が起きているとしたら、HTMLやサイト構造に問題があるサインかもしれません。見た目がきれいでも、成果につながらないケースがあるので注意が必要です。
1. 社名で検索しても検索結果に出てこない
Googleにインデックスはされているのに、自社名(いわゆる指名検索)で公式サイトが検索結果の上位に出てこない場合、HTMLの作りに課題がある可能性があります。たとえば <title> に社名が含まれていなかったり、<meta description> が適切に設定されていない場合です。さらに、重要なキーワードが画像として配置されており文字情報として検索ロボットに読み取られない、というケースも見られます。こうした状態では、検索エンジンがそのページを「公式サイト」として正しく判断できません。加えて、見出しや本文の構造が整理されていないと、ページ全体の内容が機械にうまく伝わらず、評価が下がってしまうこともあります。
また、そもそもGoogleサーチコンソールでインデックスリクエストを送っても登録されない場合は、noindex といった検索エンジンにインデックスを拒否するコードが意図せず入ってしまっているケースもあります。これでは検索結果に表示されるはずがなく、気づかないまま放置すると大きな機会損失につながります。
2. WEBサイトの表示が極端に遅い
ページの表示が極端に遅いと、それだけでユーザーはストレスを感じ、内容を読む前に離脱してしまいます。原因としては、サーバーの性能やデータセンターの設置場所、通信回線の混雑状況など、HTML以外の要因も影響します。ただし、さまざまな環境や端末で確認しても「明らかに表示が遅い」と感じる場合は、HTMLの作りが大きく関係している可能性があります。
具体的には、サイズの大きすぎる画像や不要なコードの蓄積、外部サービスの読み込みが過剰に多いことなどが挙げられます。逆にHTMLや画像の扱いが整理されていれば、同じ環境下でも体感速度は大きく改善されます。
3. レイアウトが極端に崩れてしまっている
PCではきれいに見えていても、スマートフォンやタブレットで開いたときに文字が小さすぎたり、横にスクロールしなければ読めないといったケースがあります。これはレスポンシブ対応(画面サイズに合わせて表示を調整する仕組み)が不十分なことが原因で、HTMLやCSSの調整が必要になります。見た目が崩れていると、ユーザーは読む気を失ってしまい、せっかくのコンテンツも伝わりません。
とくに企業サイトでは、アクセスの大半がスマートフォンからというケースも珍しくありません。PCでの見た目に安心せず、複数の環境で表示を確認し、必要に応じてHTMLレベルでの調整を行うことが、利用者の体験を大きく左右します。
5. 更新や修正ができない
制作者へ、ちょっとした文章の差し替えや画像の入れ替えを依頼したつもりなのに「対応が難しい」と言われたり、思いのほか高額な見積もりが提示されることがあります。その背景にはHTMLやコードの構造が整理されていないことが影響している場合もあります。本来なら簡単に直せるはずの部分が、内部の作りによっては修正が難しくなってしまケースが見られます。こうしたケースは運用の柔軟性を損ない、長期的には無駄なコストにつながる可能性があります。
初心者でも簡単にできる10分チェックリスト
特別な知識や専用ツールを使わなくても、普段のブラウザ操作で確認できるポイントがあります。ここでは「気になるときに自分で試せるちょっとしたチェック」として、代表的な項目をまとめました。
タブの名前を見てみる
ブラウザの上部に表示されるタブの文字(=titleタグ)が「トップページ」や「未設定」ではなく、会社名やサービス名になっているかを確認します。
スマートフォンで開いてみる
文字が小さすぎないか、横スクロールしなくても読めるかなど、普段どおりスマホで開いて実際の見やすさを確かめます。
文字や画像を選択してみる
ページ上の文章をドラッグしてコピーできるかどうか。コピーできない場合は、文字が画像になっている可能性があります。ロゴ画像については、右クリック→「検証」で <img> タグに alt=”会社名” のような説明が入っているかを確認します。
ソースコードをのぞいてみる
ページ上で右クリック→「ページのソースを表示」を選ぶと、HTMLの中身を確認できます。
検索(Ctrl+F/⌘+F)で <h1> を探してみて、1ページに1つだけ使われているかをチェックします。また、ソース冒頭に <meta name=”description” content=”〜”> が入っていれば、検索結果に表示される説明文が適切に設定されていることが分かります。
表示スピードを試す
PCとスマートフォンでそれぞれページを開き、Wi-Fiとモバイル回線など環境を変えてみて、もしどの環境でも明らかに遅い場合は、HTMLや画像の扱いに問題が潜んでいる可能性があります。逆に特定の環境だけ遅い場合は、サーバーや通信回線といった外部要因の影響かもしれません。
また、国外に拠点や顧客がある場合は、現地のスタッフや取引先に「どのくらいで表示されるか」を実際に試してもらうのも有効です。サーバーの設置地域によって体感速度は変わるため、現地での声を聞くことで改善の優先度を判断しやすくなります。
これらのチェックを試してみるだけでも、「見た目は整っているように見えても、内部の作りに改善の余地がある」サイトを見分ける第一歩になります。もし気になる点が見つかったら、制作会社に相談したり、専門家にコードレビューを依頼すると安心です。
まとめ
WEBサイトは見た目が整っていると完成度が高く感じられますが、裏側のHTMLに問題があると、検索に出にくかったり、表示が遅くなったり、更新や修正に余計な負担がかかることがあります。こうした課題は外からは分かりにくいため、気づかないうちに集客や信頼性に影響を及ぼしてしまうこともあります。
一方で、HTMLが丁寧に設計されているサイトは、検索エンジンにも正しく理解され、利用者にとっても快適に使えるだけでなく、将来の更新や拡張にも柔軟に対応できます。つまり、情報の意味をきちんと理解してコードへ落とし込めるかどうかが、コーダーのスキルの本質であり、その積み重ねがサイトを「長く運用できる資産」に変えていきます。
だからこそ、制作会社を選ぶときは、表面的なデザインだけでなくHTMLの品質に目を向けることが重要です。品質の高いHTMLで作られたサイトは、結果的に費用対効果が高く、企業の成長を支える強力な基盤となります。