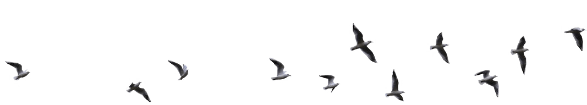2025.07.02
タイで失敗しないためのWEBブランディングとは?現地で信頼と共感を得るための5つの視点

「日本では特に広報の経験がなかったけれど、タイ駐在になった途端、WEBやSNSの管理まで任されてしまった」——そんな方も少なくないのではないでしょうか。
けれども、今のタイ市場では「何となく発信しておけばいい」という時代はすでに終わりを迎えています。今回は、WEBブランディング初心者の方でも取り組みやすい“5つの視点”から、タイ現地でWEB上における信頼と共感を得るためのポイントを解説します。
「ブランディング」と「WEBブランディング」はどう違うのか?
「ブランディング」と聞くと、ロゴやキャッチコピーのことを指すと思われがちですが、実はそれはごく一部にすぎません。
企業のブランディングとは、「この会社はどんな存在か?」「どんな価値を持っているのか?」という“企業のイメージ”を社内外に伝え、育てていく活動全体を指します。
たとえば——
・お客様にどう思われたいか(信頼感?親しみやすさ?)
・製品やサービスを通して、社会にどう貢献したいのか
・社員やパートナーに、どんな価値観を共有してほしいか
こういった“軸”をつくり、あらゆる接点——広告、店舗、営業対応、SNS、社内活動などを通じて伝えていくのが本来のブランディングです。
その中で、WEBブランディングとは、「WEBサイト」や「SNS」などオンライン上の情報発信でブランドイメージをつくる活動のことを指します。
つまり、WEBブランディングは、企業全体のブランディングの“オンライン部門”とも言える位置づけです。
とはいえ、現代では人々がまず企業を知るのは“検索”や“SNS”がほとんど。つまり、最初の印象がWEBで決まる時代になっています。だからこそ、WEBブランディングをしっかり行うことが、全体のブランディングにおいても非常に大切になってきているのです。
なぜ今、タイ市場でWEBブランディングが重要なのか
かつてのタイ市場では、「日本製」というだけで一定の信頼があり、とくに自動車や家電などの分野からくる「日本製=安心・長持ち」というイメージが根づいており、品質重視の選択肢として支持されてきました。
しかし近年では状況が大きく変わってきています。東南アジア市場全体の成熟とともに、タイにも中国・韓国・欧米など多くの海外ブランドが進出し、価格帯やデザイン、サポート体制などを含めた“総合的な価値”が比較される時代になりました。
「品質の良さ」という理由だけでは選ばれにくくなり、「翻訳しただけのWEBサイト」や「よくある日本企業の表現」では、現地のユーザーに響かないケースも増えてきています。タイ人ユーザーの感性や価値観に寄り添ったアプローチが、これまで以上に求められていると言えます。
さらに、タイ人の多くはブランド選びの際に、「この会社はどんな想いでこの商品を作ったのか」「自分の価値観に合っているか」といった“ストーリー”や“姿勢”を大切にしています。特に若い世代ではその傾向が顕著です。
つまり、製品のスペックや価格だけでなく、企業の背景や価値観まで含めて「共感できるブランドかどうか」が判断基準になっているのです。
こうした環境の中で、タイ人の感性や文化に寄り添いながら、自社の魅力や信念をきちんと伝えるWEBブランディングは、これまで以上に重要な役割を果たします。
タイ市場におけるWEBブランディングの特徴
タイでWEBブランディングを行うには、日本市場とは異なる“現地ならではの感覚”を理解しておくことが大切です。ここでは、タイ市場特有の傾向や価値観をご紹介します。
SNSが購買行動の中心に
タイでは企業の公式サイト以上に、InstagramやFacebook、TikTokなどSNSから情報を得て、商品を購入するという行動が一般的です。特に若年層の間では、SNSの投稿や広告を見て「かわいい!」「雰囲気が好き!」と感じた瞬間に、LINEやコメントで問い合わせる流れが定着しています。
そのため、SNS上の「世界観」や投稿写真の“映え方”がブランドイメージに直結します。
例:BtoCブランドがInstagramで動画やリール(短尺動画)投稿を強化 → 店舗来店数・EC売上が増加
例:BtoB企業がFacebookで施工実績を発信 → パートナー企業からの問合せが増加
若い世代は「雰囲気重視」
タイの20代〜30代は、単なる製品の性能よりも、「そのブランドの雰囲気」「ビジュアルが自分に合っているか」に敏感です。デザインが洗練されていたり、ブランドに“ストーリー性”があると、それだけで信頼されやすくなります。
つまり、「何を売っているか」よりも「どう見せているか」「なぜそれを売っているのか」が重視されるのです。
例:おしゃれなカフェのInstagramでブランド世界観に惹かれ、商品は後から知った
BtoBでも“見た目”が信頼感を左右する
「法人向けなら見た目は関係ない」と思われるかもしれませんが、タイではBtoBでもWEB上の印象がパートナー選定の決め手になることがあります。会社案内PDFが見やすいか、施工実績が整理されているか、問い合わせフォームが整っているか。これらはすべて“信頼できそうな会社かどうか”を判断する材料になります。
タイ人経営者は「ちゃんとした会社か」をまずWEBで確認します。フォームが壊れていたり、タイ語が不自然だと不信感につながることもあるので注意が必要です。
日本との文化的ギャップに注意
日本では「控えめな表現」「誠実さ」が好まれますが、タイではある程度“はっきり伝えること”“印象に残る表現”が重要です。
たとえば、日本のサイトでは「私たちは◯◯を心がけています」とぼかす表現が多いですが、タイでは「私たちは◯◯のNo.1を目指します!」と明確なビジョンを打ち出す方が共感を得られます。
また、タイ人は「楽しさ」「親しみやすさ」を重視するため、あまり堅苦しすぎるデザインや文章は、距離を感じさせてしまいます。
例:日本語版そのままのサイトでは「冷たい」「読みにくい」と言われがち。
例:親しみのある言葉づかいや、カジュアルな写真の方が反応が良い傾向。
タイ市場でのWEBブランディングでは、「タイ人ユーザーはどこで情報を得て、どう感じ、どう行動するか」を知ることが出発点です。日本での常識にとらわれず、現地の感覚に寄り添った表現と構成が求められます。
タイ市場でのブランド構築に必要な5つの要素
タイ市場でWEBブランディングを成功させるには、単に「見た目を整える」だけでは足りません。ユーザーに信頼され、共感されるためには、戦略的に「どう見せるか」「どう伝えるか」を考える必要があります。
ここでは、タイ市場で特に意識したいブランド構築の5つの基本要素を、具体的な視点からご紹介します。
1. トーン&マナーの統一感
ブランディングでは、「どんな口調で、どんな雰囲気で話すか(トーン)」と「その雰囲気をどこまで守るか(マナー)」の統一が非常に大切です。
特にタイでは、丁寧すぎる日本語の直訳だと距離感が生まれてしまうことがあります。柔らかくて親しみのあるタイ語表現に言い換えるだけで印象が大きく変わります。
例:
・× ロゴやフォント、写真のトーンがバラバラ → ○ 全体のトーンを揃えて世界観を統一
・× 文章の語り口が媒体ごとにバラバラ → ○ 一人称や語調を統一して親しみやすく
また、本社サイトと連動させる場合も、“同じように見せる”のではなく、“現地に合わせて馴染ませる”ことがポイントです。
2. 現地ニーズを捉えたビジュアル戦略
タイ人ユーザーは「目で感じる」感性がとても豊かです。そのため、デザインや写真選びは「機能的かどうか」以上に「魅力的に見えるか」「親しみを感じられるか」が重要になります。
ヒント:
・モデルはタイ人を使うとリアリティが高まり、親近感が生まれる
・明るい配色やポジティブな表情の写真が好まれる傾向
・フォントは可読性だけでなく、“やさしさ”や“安心感”を演出する道具
また、「映える」感覚に合った構図や余白の使い方も、SNSなどでの拡散力に直結します。
3. “共感”を得るストーリーテリング
ブランドの価値は、商品そのものだけでなく「どんな背景や想いがあるのか」によって強くなります。
伝えるべきストーリーの例:
・なぜこの製品やサービスを作ったのか
・どんな課題を解決したかったのか
・タイでの挑戦や、現地スタッフとの取り組み
特に、現地の声や実例を交えると説得力が増します。ユーザーインタビューやスタッフ紹介をコンテンツに取り入れるのも有効です。
例:
「タイのスタッフの提案で生まれた改善点が、実は現地のお客様にも大好評でした」
4. UX/UIにおける信頼感の演出
WEBサイトの使いやすさや視認性も、ブランドに対する信頼感に直結します。たとえデザインがきれいでも、読みづらかったり、問い合わせしづらい構成では、ユーザーはすぐに離れてしまいます。
チェックポイント:
・タイ語表示の自然さ(翻訳の不自然さは信頼を損なう)
・スマートフォンでの閲覧時に文字が読みやすいか
・問い合わせボタンが目立っていて、1クリックでたどり着けるか
・読み込みスピード(とくにモバイル環境では重要)
また、SNSやLINEからの導線も含めたユーザーの動線設計を行うことで、「迷わず問い合わせまで進める」サイトになります。
5. 継続的な発信と顧客との対話
ブランディングは一度作ったら終わり、ではなく「育てるもの」です。更新されていないSNSや古い情報のままのWEBサイトは、逆にマイナスイメージを与えることもあります。
実践例:
・InstagramやFacebookで週1回でも定期的に投稿
・LINE公式アカウントでキャンペーン情報や豆知識を配信
・コメントやメッセージへの返信を通じて、ユーザーとの接点を増やす
こうした小さな「対話」を積み重ねることで、ブランドはより“人間味”のある存在として、タイのユーザーに受け入れられていきます。
グローバルなWEBブランディングの本質は“翻訳”ではなく“通訳”
グローバル市場に向けてWEBで発信する際、多くの企業がまず「日本語の資料を英語や現地語に翻訳すること」から始めます。もちろんそれ自体は必要なプロセスですが、翻訳だけでは、本当に伝えたい価値が正しく届かないこともある——これがグローバルWEBブランディングで陥りやすい落とし穴です。
「本社の資料を訳せば伝わるはず」と思ってしまいがちですが、大切なのは「相手がどう受け取るか」。
つまり、「伝えたいことを、相手の文化や感性に合わせて“伝わる形”で表現する」ことが、グローバルなWEBブランディングの本質です。
たとえば、日本語では控えめで誠実な印象を与える表現も、英語圏やアジア圏では遠回しでわかりにくく映ることがあります。逆に、日本では派手すぎると感じられる色づかいや演出が、他の国では“魅力的で明快”と受け取られることもあります。
WEBサイトやSNSは「文化の境界線上にあるコミュニケーションの場」です。
だからこそ、“正確に訳す”だけではなく、“どんな表現なら共感されるか”という視点で情報を設計する必要があります。
グローバルなWEBブランディングとは、相手の文化を理解しながら価値を伝える“通訳”のような行為なのです。
WEBは“共感”と“信頼”のための場所
タイでのWEBブランディングは、決して特別なテクニックが必要なものではありません。「相手に伝わるように表現する」——その基本をおさえ、現地の文化や感性に少しずつ歩み寄ることで、着実に信頼と共感は育っていきます。
もし社内にノウハウがない場合は、「現地理解」に長けた制作パートナーと組むのも一つの方法です。WEBは“一方通行の広告”ではなく、“対話を生む場”として、じっくり育てていきましょう。
関連記事
-

タイでWEBサイト制作・運営をする上で、気をつけるべきタイスタッフとのコミュニケーションのポイント
タイに進出する日本企業では、現地でのWEBサイト制作や運用をタイ人スタッフに中心的に担ってもらうケースが増えています。現地スタッフの力を最大限に引き出しながら、企業として一貫性のあるWEBサイトを構築・運用していくために意識しておきたいポイントをご紹介します。
2025.05.18 #WEBサイト制作 -

タイBtoB市場におけるデマンドジェネレーションの活用とその有効性
タイでBtoB企業の市場拡大、拡販をしたいとお考えのマーケティング担当者の方の中にデマンドジェネレーションを活用したいという方が増えています。 ここでは、デマンドジェネレーションの基本的な考え方をはじめ、タイ市場においてデマンドジェネレーションを活用する際の留意点などをご紹介したいと思います。
2024.02.17 #デジタルマーケティング -

タイで新規にWEBサイト制作を行う際に適したドメイン選びのポイント
タイで新たにWEBサイトを立ち上げる際に「ドメインをどうするか」で悩まれる方も多いかと思います。 WEBサイトの成功には多くの要因が影響しますが、その基盤となるのは適切なドメインの選択です。特にタイの市場を対象にした場合に考慮すべきポイントをご紹介します。
2023.11.02 #WEBサイト制作#WEB・広報担当者のための基礎知識 -
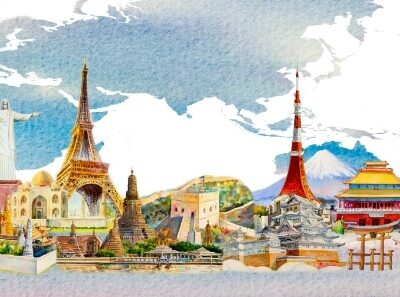
タイと日本のクロスカルチャーをデザインの視点から考える
タイと日本は、それぞれが異なる歴史の影響を受けて進化した文化や価値観を持つ国々であり、それぞれに独自性があります。タイと日本の間でよりボーダレスな価値の共有促進を考えるために、タイと日本とのクロスカルチャーをデザインの視点から考えてみたいと思います。
2023.10.06 #デザイン・UI/UX