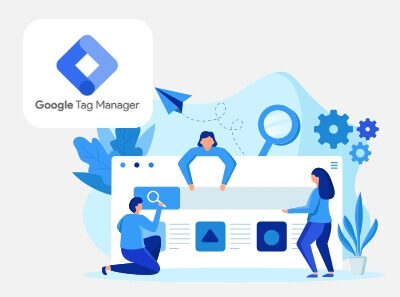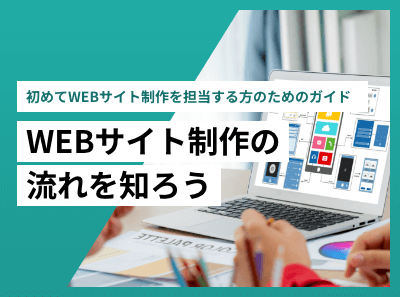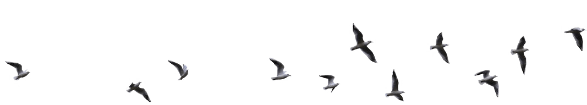WEBサイト制作に入る前に準備しておきたいこと ― 初めてWEBサイト制作を担当する方のためのガイド
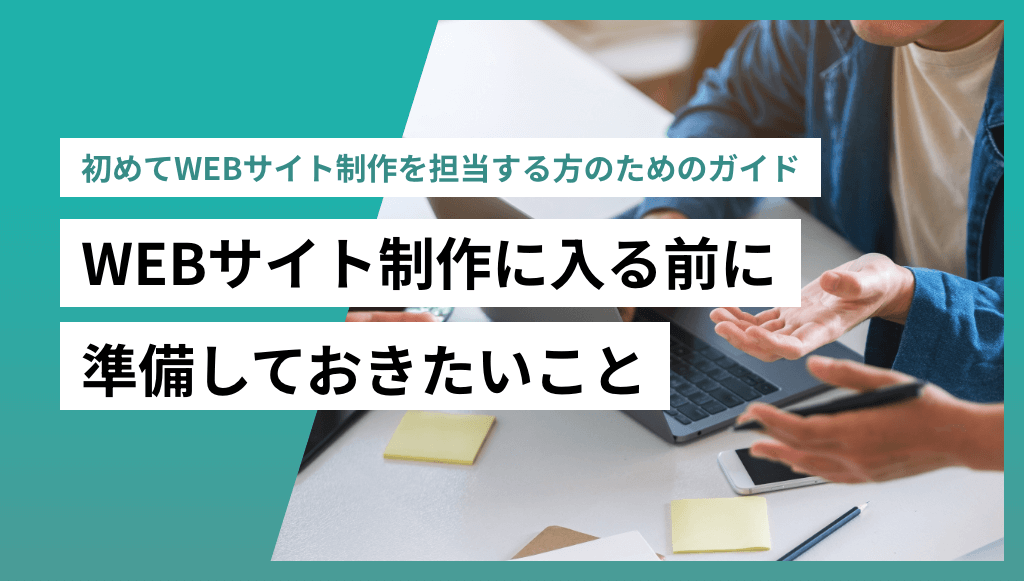
WEBサイトの制作やリニューアルを任されたとき、最初に悩むのが「何から手をつければいいのか」という点ではないでしょうか。いきなり制作会社に相談しても、社内で方向性がまとまっていないと打ち合わせが空回りしてしまうこともあります。だからこそ、着手前に社内で準備をしておくことが大切です。目的やターゲット、載せたい内容が共有されていれば、その後の進行はぐっとスムーズになり、より効果的なサイトづくりにつながります。
とくに制作パートナーと打ち合わせを始める前に、次のようなポイントを社内で話し合っておくと、要望が明確になり、提案の質も高まりやすくなります。
制作前に社内で準備しておきたい6つのポイント
WEBサイト制作やリニューアルを成功させるためには、デザインや技術だけでなく、着手前の“社内準備”が欠かせません。
現状の課題を洗い出し、目的を明確にし、成果の測定方法や予算、運用環境を整理しておくことで、制作パートナーとの打ち合わせもスムーズになり、的確な提案を受けやすくなります。
この記事では、制作前に社内で話し合っておきたい8つのポイントを順に解説します。
8つのポイント
【1】今のサイトや営業活動のどこがうまくいっていないか考える
【2】自社の強み(USP)を洗い出す
【3】新しくつくるサイトで、何を実現したいか話し合う
【4】参考・競合サイトを調べ、イメージを共有する
【5】サイトの効果をどう測るか、目安を考えてみる
【6】使える予算や費用の上限を考えておく
【7】今のドメインやサーバーをそのまま使うか、変えるか確認
【8】あわせて確認しておきたい:Googleアカウントの管理状況の確認
では、まず【1】現状の課題整理から見ていきましょう。
【1】今のサイトや営業活動のどこがうまくいっていないか考える
WEBサイトの制作やリニューアルを考えるとき、まず取り組みたいのが「現状の棚卸し」です。
つまり、今のサイトや営業活動のどこが課題なのかをしっかり見つめ直すことからスタートします。
なぜこれが重要かというと、課題が見えていないまま制作に進むと、「見た目はきれいだけれど成果が出ないサイト」になってしまう可能性があるからです。
改善すべきポイントをはっきりさせておけば、どんな情報を強調すべきか、どの導線を見直すべきかが具体的に見えてきます。
たとえば、次のような点をチェックしてみましょう。
問い合わせ数が少ない
→ 問い合わせページがわかりにくい? 説明不足? 信頼感が足りない?アクセス数はあるが反応がない
→ 誘導の導線が弱い? 伝えたい内容がずれている?スマートフォンで見づらい
→ モバイル対応が不十分? 読みにくい? ボタンが小さい?内容が古く、更新されていない
→ 商品情報や組織体制が変わっていて実態と合っていない?
このように「見た目」ではなく、「成果」や「使いやすさ」の視点から、営業担当や社内の他部門とも連携して広く意見を集めておくと、より実効性のあるリニューアル方針を立てることができます。
また、こうした課題は、制作会社にとっても非常に参考になる情報です。単なる要望ではなく、「なぜそれが必要なのか」が伝わると、より本質的な提案を受けやすくなります。
【2】自社の強み(USP)を洗い出す
WEBサイトの目的を考える前に、まずは「自社の強み」をはっきりさせておくことが大切です。ここでいう強みとは、競合にはない特徴や、自社ならではの価値のこと。マーケティングの言葉で「USP(Unique Selling Proposition)」とも呼ばれます。
強みを整理しておくと、サイトの方向性がぶれにくくなり、伝えるべきメッセージが明確になります。逆にこれが曖昧なまま進めてしまうと、デザインや文章のトーンが定まらず、どこにでもあるサイトになりかねません。
どうやって洗い出すのか?
強みは「自分たちが思っていること」と「お客様が感じていること」の両方から考えるのがおすすめです。例えば以下のような観点があります。
商品・サービスの特徴
他社より優れている性能や、独自の技術、提供スピードなど。価格や提供方法
コストパフォーマンスや、サポート体制の手厚さなど。企業姿勢や実績
創業年数や取引実績、社会的な信頼性や地域密着度。
書き出してみることが重要
いきなり「これがUSPだ」と一つに絞る必要はありません。まずは箇条書きでも構わないので、社内で意見を出し合い、思いつく限り書き出してみましょう。
その際、「強み」だけでなく「弱み」や「デメリット」だと感じている点もあえて挙げてみることがポイントです。
なぜなら、社内では短所だと思っていても、見方を変えれば個性や特色として評価される場合があるからです。
たとえば「小規模で人員が少ない」という点は、裏を返せば「小回りがきき、柔軟な対応が可能」と言い換えられます。
こうして「プラス面・マイナス面の両方」を整理することで、自社を客観的に捉えられ、外部に伝えるべき価値がより明確になります。
強みを明確化したうえで、市場における立ち位置を整理したい方は、こちらの記事も参照ください。
【3】新しくつくるサイトで、何を実現したいか話し合う
WEBサイトは、単なる会社案内ではなく、「目的を達成するための手段」としてつくるべきものです。だからこそ、「なぜ今、新しくサイトをつくるのか?」「このサイトで何を実現したいのか?」というゴール設定が、最初の段階でとても重要になります。
目的がぼんやりしたまま制作を始めてしまうと、ページ構成やデザイン、導線設計も曖昧になり、「誰のためのサイトか分からない」「作ったけど成果につながらない」といった事態にもつながりかねません。
まずは、以下のような観点から、自社にとっての“達成したいことを社内で話し合ってみましょう。
たとえば
新しいお客様からのお問い合わせを増やしたい
→ 製品・サービスの魅力がしっかり伝わる構成にする
→ 問い合わせ導線を目立たせる採用ページをわかりやすくして、応募数を増やしたい
→ 会社の雰囲気や働く人の声を伝えるコンテンツを加える
→ 応募のハードルを下げる仕組みにする海外の顧客にもアピールしたい(多言語対応など)
→ タイ語・英語などの切り替え機能を入れる
→ 海外拠点や対応可能エリアの情報を追加する名刺代わりではなく、営業に使える“伝えるツール”にしたい
→ サービスごとの強みや事例を充実させる
→ 営業先に見せてもわかりやすい設計にする
こうした「何を実現したいか」が明確になると、その後のサイト構成やデザインもブレずに組み立てることができます。また、制作会社に依頼する際にも、具体的な要望として伝えやすくなり、より目的に沿った提案や改善策が期待できます。
目的は1つである必要はなく、複数あっても構いません。ただし、「どれが一番大事か」の優先順位は決めておくと、制作時の判断がスムーズになります。
【4】参考・競合サイトを調べ、イメージを共有する
自社の強みを整理したら、次は「他社や参考になるサイト」を見てみましょう。
特に新しいサイトをつくるとき、最初からゼロベースで考えるのは難しいものです。実際に公開されているサイトを見比べることで、どんな表現や構成が一般的なのか、自社にとって取り入れたい要素は何かが見えてきます。
競合サイトを調べる意味
同じ業界の競合サイトを調べることは、業界全体のスタンダードを知る上でとても重要です。たとえば、どのようにサービスを紹介しているか、どんなページ構成になっているかを見ることで、外してはいけない基本的な要素を把握できます。また、似たような表現が多く並ぶなかで、自社ならではの違いや強みをどう打ち出すかを考えるきっかけにもなります。つまり競合サイトの調査は、単に真似をするのではなく、差別化のポイントを見つけるためのヒントになるのです。
参考サイトを探す意味
一方で、必ずしも競合だけに絞らず、参考になるサイトを幅広く探すことも有効です。異業種のサイトや海外の事例などは、自社にはなかったデザインの発想や見せ方を学べる貴重な素材になります。さらに、参考サイトを見ながら「こういう雰囲気は合う」「この見せ方は避けたい」と意見を出し合うことで、自社の方向性を具体的に言葉にしやすくなります。参考サイトはつまり、デザインや表現の引き出しを増やし、社内の共通認識を形づくるためのツールと言えるでしょう。
イメージを共有するメリット
社内の関係者それぞれが「こんなサイトにしたい」と考えていても、頭の中のイメージは人によって異なります。そこで実際のサイト例を見ながら話すことで、感覚的な部分を具体的に共有でき、制作の方向性が大きくぶれるのを防ぐことができます。特に「良いと思う例」と「避けたい例」の両方を出しておくと、自社にふさわしいデザインや伝え方が自然と浮かび上がってきます。
【5】サイトの効果をどう測るか、目安を考えてみる
WEBサイトは「つくって終わり」ではなく、「公開したあと、どれだけ役に立っているか」を見ることが大切です。
そのためには、「効果をどうやって測るか」という目安=ゴールのイメージを、事前に持っておくことが重要です。
これがないと、「良いサイトができたけど、本当に成果が出ているのか分からない」「次に何を改善すればいいか判断できない」といった状態になってしまいます。
たとえば、以下のように「成果が出た」と感じられる具体的な状況をイメージしてみましょう。
毎月5件以上のお問い合わせがくると嬉しい
→ 目標:月5件の問い合わせ採用ページから1ヶ月に1人応募があるとよい
→ 目標:月1件の応募製品ページのアクセス数が今の2倍になると効果を感じる
→ 目標:アクセス数●件以上資料請求ページの送信率を増やしたい
→ 目標:ページ閲覧数のうち、●%が資料請求に進む
最初はざっくりとした感覚でも大丈夫です。「こんな状態になったら嬉しいな」という基準を考えるだけでも意味があります。
なぜ目安が必要なのか?
目安を決めておくことは、WEBサイト制作を“効果につながる取り組み”にするために欠かせません。
サイトは「つくって終わり」ではなく、「公開してからがスタート」です。どれだけ綺麗に仕上がっても、それが見られなかったり、反応がなければ、ビジネスにはつながりません。
そのため、あらかじめ「どんな変化があれば成功といえるのか」「どうなったら成果が出たと判断できるのか」といった目安を持っておくことで、完成後の振り返りや改善がしやすくなります。
たとえば、「月に5件の問い合わせがほしい」という目安があれば、実際に公開してから「今は3件だから、あと2件増やすにはどこを直すべきか?」というように、具体的な改善の糸口が見えてきます。
逆に、目安がまったくないと、「サイトはできたけど、これで良いのかよく分からない」「次に何をすればよいのか見当がつかない」と、動きが止まってしまいがちです。
また、目安があると、制作会社とのやりとりでも「どこを重視してつくるべきか」が共有しやすくなり、目的に合った提案が受けられるようになります。
たとえば「問い合わせを増やしたい」という目的がはっきりしていれば、構成や導線の設計、CTA(行動を促すボタン)の工夫など、目的達成に向けた具体的なアドバイスが得やすくなります。
つまり、目安を持つことは、成果の見える化にもなり、社内外の共通認識をつくるうえでもとても大切なステップなのです。
なお、目安の立て方に不安がある場合でもご安心ください。
弊社では、ご依頼時に現在の状況のヒアリングや、目的に応じた目標設定のご相談も含めてサポートいたします。
【6】予算の目安を決めておく
予算をあらかじめ想定しておくことは、制作を安心して進めるための大切な準備です。金額の目安があると、途中で「想定以上に費用がかかり、機能を削らざるを得ない」といった事態を防げます。
予算を決めておくことで得られるメリットは多くあります。
・デザイン・機能・コンテンツなど、どこに重点を置くかの優先順位をつけやすい
・各社の提案や見積もりを比較しやすい
・実現できるサイト規模や機能を現実的にイメージできる
・金額面での調整に振り回されず、スケジュールがスムーズに進む
・初期費用と運用費を分けて考えることで、公開後の改善計画を立てやすい
とはいえ、「相場がわからないから予算を立てられない」というケースも少なくありません。その場合は、最初に制作会社へ「予算感を知りたい」と率直に相談してみるのも一つの方法です。複数社に問い合わせれば、だいたいの価格帯が見えてきますし、その上で自社としての上限を設定していけば大丈夫です。
さらに、とくに海外で制作する場合には注意が必要です。コストを重視するあまり、現地の安価な制作会社に依頼した結果、品質やサポートに不満が残ったという声も少なくありません。実績やサポート体制を確認し、価格だけで判断しない視点を持つことも大切です。
【7】今のドメインやサーバーをそのまま使うか、変えるか確認
WEBサイトをリニューアルする場合、今使っている「ドメイン(例:www.example.com)」や「サーバー(ホームページを置いている場所)」をどうするかも、事前に確認しておきたいポイントです。
これらはWEBサイトの“土台”とも言える部分で、使い慣れているものをそのまま活用するのか、新しくした方がよいのかによって、費用や作業内容が大きく変わってきます。
事前に把握しておくことで、制作会社とのやりとりもスムーズになり、「途中で思わぬ追加費用が発生する」といったリスクも避けやすくなります。
確認しておきたいことの例
今使っているドメインは何か?
→ 自社で管理しているか、他社(制作会社など)に任せているか確認しておきましょう。契約しているサーバーはどこか?
→ レンタルサーバー(例:さくらインターネット、Xserver、ロリポップなど)か、独自の環境かをチェックします。更新日や契約者情報は誰か把握しているか?
→ ドメインやサーバーの契約者が退職してしまっていた…というケースも意外と多いため、現在の管理体制を明確にしておくことが重要です。新しいサイトをつくるときに今の環境で対応できるか?
→ 古いサーバーだとCMS(WordPressなど)が動作しない、常時SSL化(https対応)できない、といった制約がある場合もあります。
【8】あわせて確認しておきたい:Googleアカウントの管理状況の確認
WEBサイトの効果測定やアクセス解析に使われる「Googleアナリティクス」や「Googleサーチコンソール」は、多くの企業サイトに導入されています。
これらのツールが既に使われている場合は、
・ログインできるGoogleアカウントが社内にあるか?
・どのアカウントが管理者になっているか?
・過去のアクセスデータは引き継げるか?
といった点を確認しておくことが大切です。
アカウントの管理者が不明だったり、個人の私用アカウントで設定されていると、後で引き継ぎができずに困るケースもあります。
ご不明な場合も、お気軽にご相談ください
「ドメインやサーバーのことはよく分からない」「Googleアカウントがどれか曖昧…」という方も多いと思います。
弊社では、ご依頼時にこれらの情報整理や確認作業も丁寧にサポートしております。必要に応じて移管や再設定のご相談にも対応可能ですので、安心してご相談ください。
まとめ
WEBサイト制作やリニューアルを成功させるには、デザインや機能の前に“社内準備”を整えることが大切です。今回ご紹介したポイントも、すべてを完璧にそろえる必要はなく、まずはできるところから整理していく姿勢で十分です。
重要なのは、社内で「何を実現したいのか」「どんなイメージを持っているのか」を共有しておくこと。その土台があるだけで、制作の打ち合わせは具体的になり、完成後の活用も格段にスムーズになります。
また、サイトの役割は企業や状況によって大きく変わります。会社案内として基本情報を発信する場合もあれば、サービスや商品を紹介して顧客獲得につなげたい場合、採用活動を強化したい場合など、目的はさまざまです。どのタイプのサイトであっても、事前に方向性を整理しておけば、公開後の改善や更新も迷わず続けられます。
そして何より、準備を進める過程そのものが、社内の理解や意識を深める機会になります。部門間で視点を出し合い、課題や強みを言語化することは、単にサイトを作るためだけでなく、今後の事業戦略や日々の活動にも役立つはずです。WEBサイトをきっかけに社内がひとつの方向を向ければ、完成後の効果は自然と大きく広がっていきます。